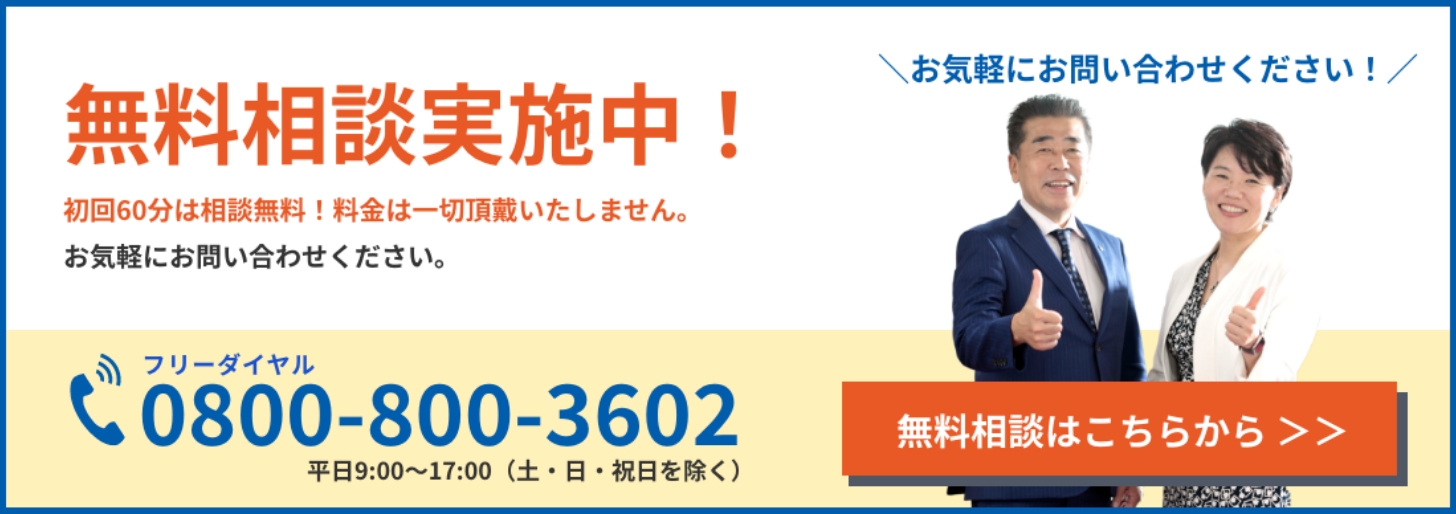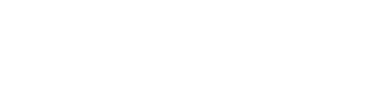一時所得を確定申告しないとどうなる?|「一時所得とは何か」「確定申告をする必要がある条件」「計算方法」「ペナルティ」についても言及
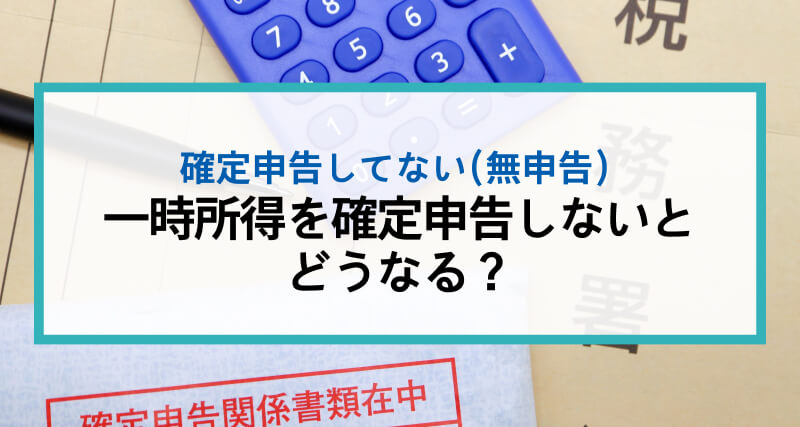
目次
本記事は、「一時所得がある」方に向けて、「一時所得を確定申告しないとどうなるか」について理解できるように、一時所得全般に関して網羅的且つ簡潔に解説しています。
一時所得にも、様々な種類があります。
しかし種類に関わらず、多くの場合確定申告が必要であり、申告せずに放置していた場合、「無申告加算税」などの罰金が課せられます。
そこで今回は、
- 一時所得には具体的にどのようなものがあるのか
- 一時所得で確定申告をしなければいけない対象は誰か
- 確定申告をしないとどうなるのか
について詳しく解説します。
個人事業主の方が、確定申告をしていない(無申告)場合どうなるのかをまとめた記事はこちらです。合わせてご覧ください。
1.一時所得とは
一時所得は、以下の4要件にあてはまるもののことを指します。
①一時的な所得であること(継続的な所得ではないこと)
②労働により得た所得ではないこと
③資産の売却により得た所得ではないこと
④営利を目的とし、なおかつ継続的な行為から得た所得ではないこと
なお、「所得」と呼ばれるものは、全部で10種類あり、それぞれ税額の計算式が異なります。
10種類の所得区分については、以下の国税庁のページで確認できるので興味があれば確認してみてください。
一時所得にあてはまるもの
一時所得に該当するものは以下の通りです。
一時所得にあてはまるもの 一覧
- 懸賞やクイズなどでもらった賞金や商品
(ただし、個人事業主が仕事を通じて得た所得については、事業所得に該当) - 競馬、競輪で得た払戻金
- 生命保険の満期保険金
(ただし、年金形式で受け取る場合は、雑所得に該当) - 長期損害保険の満期返戻金
- 法人から贈与された金品
- 借家人が立ち退きの際にもらう立退料
(ただし、借家人が商売をおこなっていて得た売上補填などの名目にあたる所得の場合は、事業所得に該当) - 遺失物を届けた際にもらった謝礼金
なお、宝くじが当たった場合の当選金は非課税なので、確定申告の対象とはなりません。
また、上記いずれかに該当するものであっても、一定条件にあてはまらなければ確定申告の対象ではありません。
この条件については後ほど解説します。
雑所得と贈与との違い
「一時所得」と間違えそうなものに、「雑所得」と「贈与」があります。
「一時所得」「雑所得」「贈与」の違いは以下のとおりです。
| 所得の種類 | 概要 |
|---|---|
| 一時所得 | 労働以外の手段で得た所得で、一時的に得たもの |
| 雑所得 | 労働により得た対価など |
| 贈与 | 親などの個人からもらったお金など |
雑所得にあてはまるもの
具体的には、下記のようなものが「雑所得」に該当します。
雑所得にあてはまるもの 一覧
- 個人年金・公的年金
- 生命保険の満期保険金を年金形式で受け取るもの
- インターネットを利用しアフィリエイトなどで得た収入
- 原稿料や講演料
- 株主優待券
- 商品先物取引・金融商品先物取引による所得
など
「一時所得」は、労働以外の手段で得た所得で、なおかつ一時的に得たものが対象となりますが、「雑所得」は、労働により得た対価などが該当します。
贈与にあてはまるもの
具体的には、下記のようなものが「贈与」に該当します。
贈与に該当するもの 一例
- 親が子供のためにマイホームを購入
- 親が子供のために結婚や大学の資金援助を行う
上記のように親などの個人からもらったお金は「贈与」であり、「一時所得」ではありません。
年間110万円を超える財産を貰った場合に「贈与税」の対象となります。
ただし、個人ではなく法人からもらったお金は、贈与ではなく一時所得として課税されますので注意してください。
2.一時所得の計算方法
一時所得の課税所得金額の計算式は以下のとおりです。
一時所得の課税所得金額
=(総収入金額-必要経費-特別控除額)×1/2
なお、一時所得の「特別控除額」は、
「総収入金額-必要経費」が、
- 50万円未満の場合は、その全額
- 50万円以上の場合は、50万円
となります。
ちなみに、「必要経費」とは、一時所得の金額を得るためにかかった経費のことを指します。
たとえば生命保険の場合、毎月支払っていた払込保険料などが経費に該当します。
そのため、払込保険料を差し引いた結果が50万円以下となった場合、税金はかかりません。
一時所得がマイナスだった場合は確定申告不要
例えば貯蓄型保険に加入していたものの、低金利のため実際に払い込んだ保険料よりも「返戻金が少なくなった」という場合があります。
この場合、受け取った総額よりも、支払った保険料のほうが高いため、結果的に一時所得がマイナスとなり、「所得がゼロ円」となるため確定申告の対象外となります。
なお、一時所得は、同じ一時所得同士であれば損益通算ができます。
そのため、例えば馬券で得た払戻金があり、一方、保険でマイナスがある場合は、これらを損益通算して赤字分を差し引くことができます。
ただし、他の所得との損益通算はできないので注意してください。
3.一時所得で「確定申告をする必要がある」条件
一時所得が50万円を超えた場合は、確定申告をしなければいけない対象となります。
ただし、一時所得が50万円以下であったとしても、以下に該当する場合は確定申告が必要です。
- 年収が2,000万円以上ある場合
- 給与所得以外の所得があり、合算して20万円以上ある場合
- 2か所以上の事業所から給与を受け取っている場合
(年末調整は1事業所でしか行うことができないため)
4.確定申告対象なのに一時所得の確定申告をしないとどうなるか
「一時所得が50万円以上ある」など確定申告を行わなければいけない対象であるにも関わらず、確定申告をしないと、
厳しい罰則があり、高い罰則金を支払うことになってしまうので注意してください。
1:無申告加算税
一時所得があるにもかかわらず確定申告をせずに放置していた場合、「無申告加算税」が課せられます。
無申告加算税は、納付すべき税額に対し、
「50万円までは15%」、「50万円を超える部分は20%」の割合を乗じて計算した金額です。
ただし、確定申告の期限が過ぎた後でも、自主的に確定申告をした場合は、無申告加算税が軽減され、「5%の割合を乗じて計算した金額」になる場合があります。
確定申告対象であることがわかっている場合は、必ず期限内に確定申告を行うべきですが、万が一その期限が過ぎていたとしても、税務署の調査が入る前に申告を行いましょう。
2:延滞税
支払うべき税金があるにもかかわらず、定められた期限までに納めなかった場合、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じ、「延滞税」が課せられます。
納税額は、「滞納額」と「期間」によって変わります。
国税庁のWebサイトで、シミュレーションができるので、気になる方は以下で確認してみてください。
3:改ざんや偽造など悪質な場合は刑事罰
所得金額を実際よりも少ない金額で申告をしたり、あるいは隠したりする行為は「脱税」にあたります。
「脱税」は、
追徴課税が課せられるのに加え、刑事罰も科せられる場合があります。
確定申告の偽造は立派な違法行為ですので、絶対にしないでください。
確定申告をしていない場合のペナルティ(罰金)について、以下の記事でより詳しく解説しています。
【個人事業主向け】「確定申告をしていない(無申告)」 まとめ記事
【個人事業主向け】「確定申告をしていない(無申告)」 関連記事
- 【個人事業主向け】「確定申告をさかのぼって行う」方法を解説|期限後申告・無申告解消の仕方&必要書類一覧
- 【収入源別】確定申告は必要か?確定申告をしない(無申告)とどうなる?一覧|メルカリ、株、ウーバーイーツなど
- メルカリで稼ぎがあっても確定申告しなかったらどうなる?|「確定申告をしなかった場合のペナルティ」「確定申告をしないとバレるのか」「確定申告時の注意点」も言及
- ウーバーイーツの稼ぎも確定申告をしないといけないのか?|確定申告の注意点、必要性についても解説
- 株を売却して得た利益を確定申告しないとどうなる?|「不要なケース」や「したほうが得なケース」「申告方法」についても解説
- YouTubeでの稼ぎは確定申告が必要か|「確定申告しなかった場合のペナルティ」「確定申告しなくて良いケース」等について解説
- バイトの掛け持ちは「年収103万円超え」で確定申告が必要|バイトの掛け持ちが会社にバレない方法も解説
- クラウドワークスでの収入は確定申告する必要があるか|確定申告しないとどうなるか、確定申告が必要ないケースも解説
- 副業して確定申告をしないとペナルティはある?|「確定申告をする必要があるケース」「本業の会社にバレない方法」も紹介
- 一時所得を確定申告しないとどうなる?|「一時所得とは何か」「確定申告をする必要がある条件」「計算方法」「ペナルティ」についても言及
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
最近の投稿
- 2026.02.25
- リーダーシップへの舞台裏Vol.29 ~今を駆ける社長のインタビューシリーズ~
- 2026.01.30
- 税務調査で「追徴課税」になったら、いくら、いつまでに納めるのか?
- 2026.01.13
- リーダーシップへの舞台裏Vol.28 ~今を駆ける社長のインタビューシリーズ~
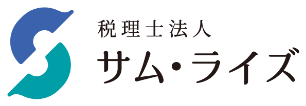
 0800-800-3602
0800-800-3602 お問い合わせ
お問い合わせ アクセス
アクセス