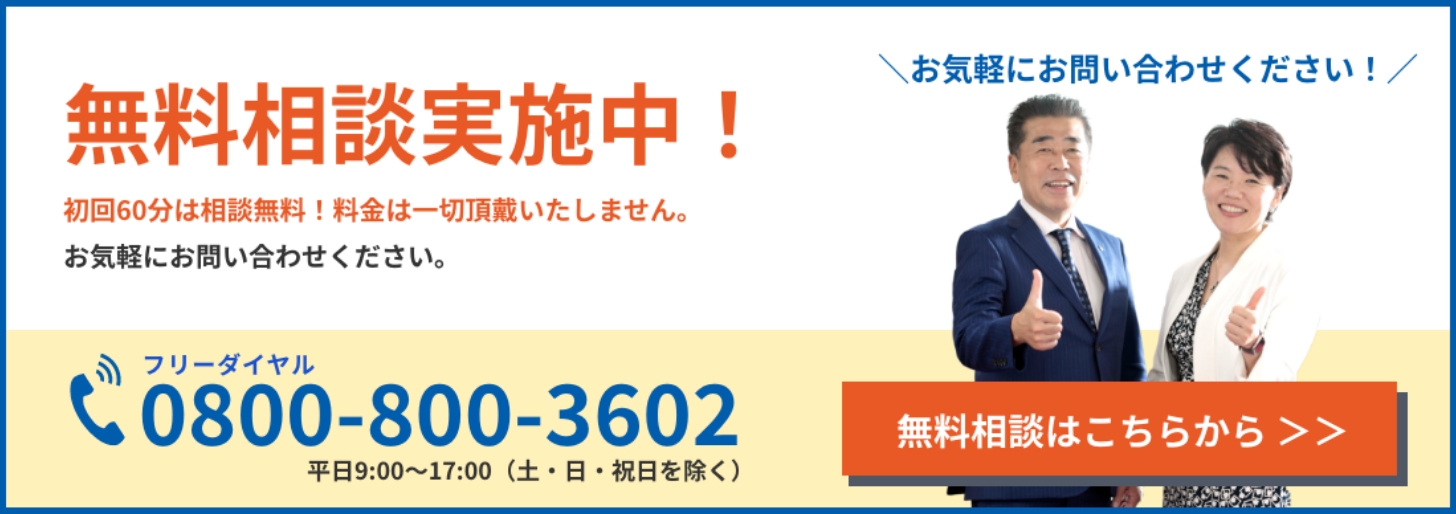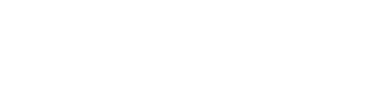【無申告の罰金強化決定】ペナルティの内容・対策方法を徹底解説

目次
令和5年度の税制改正法案が成立しましたが、予想通り令和5年度税制改正大綱の内容が踏襲されました。
今回の税制改正では、「課税・徴収関係の整備・適正化」として無申告者への罰則強化が盛り込まれています。
この記事では、罰則強化の背景を踏まえながら、ペナルティの内容や対策方法を徹底解説します。
無申告への罰則強化の背景とその意義
日本の所得税は、納税者自らが所得の確定申告を行うことを原則とする「申告納税制度」となっています。
つまり国税当局も「所得のある人は申告するはず」という性善説に立っているのですが、ご存知のように申告をしない「無申告」の事例が後を絶ちません。
まずは、この現状と罰金強化決定の背景を確認してみましょう。
国税庁の重点調査項目
国税庁の取り組みについて毎年発表している「国税庁レポート2022」を見ると、最近の税務調査の傾向が分かります。
そこには当たり前の取り組みとして、「正に税金の負担を逃れようとする悪質な納税者に対しては、適切な調査体制を編成し、厳正な調査を実施することとしています」とあり、具体的に以下を重点調査項目としています。
- 消費税の適正課税の確保のため、十分な審査と調査を実施
- 資産運用の多様化・国際化を念頭に置いた調査を実施
- 資料情報を活用し、的確に無申告者を把握
- シェアリングエコノミー等新分野の経済活動への的確な対応
無申告者を逃さないのは当然として、見て分かるとおり仮想通貨などの資産運用や、いわゆる「副業」への課税強化を打ち出しています。
多様化する個人所得
長年個人所得が伸び悩むなか、国の施策として資産運用への優遇措置や、副業などの推奨が行われています。
そして推奨したうえでの課税強化なので、国民感情としては「?」となりますが、個人が所得を得る手段の多様化は国税庁とのイタチごっこの様相を呈しているのが現実です。
この多様化と無申告には一定の相関関係があり、申告納税義務を負うべき人が飛躍的に増えています。
2023年3月に、動画をユーチューブに投稿し、その報酬を申告していなかった男性が税務調査を受け、重加算税を含む約700万円を追徴課税された事例がありました。
当のユーチューバーは、「確定申告が必要なことを知らなかった」という趣旨の説明をしていたようですが、申告納税制度でその言い訳は通用しません。
個人が何らかの利益を得るときは、必ず課税関係が付きまとうことを意識する必要があります。
適正公平な課税徴収の実現
日本に住んでいる以上、日本国憲法第30条の「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」を遵守しなければなりません。
税金は、国や地方団体を維持し、発展させていくために欠かせないもので、無申告者の放置は税金に対する不公平感を生んでしまいます。
簡単にいうなら、無申告者のような不心得者を懲らしめるための罰則強化が盛り込まれたのが、今回の令和5年度税制改正法です。
無申告に対するペナルティの内容
令和5年度の税制改正法では、無申告に対して2つのペナルティが追加されました。
一つは従来からあった「無申告加算税」の見直しで、もう一つは「繰り返し行われる無申告」への加重措置の新設です。
ここでは、それぞれの内容について詳しく解説します。

無申告加算税の改正
無申告加算税は、法定期限内に確定申告をしなかった場合、つまり無申告者に課される税金で従来からあったものです。
課される税額は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
ただ調査の事前通知の後に申告した場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額に減額されます。
つまり税務調査を受けた後の申告が、一番高い無申告加算税を課されるということです。
これを一覧にすると以下のとおりとなります。
| 50万円まで | 50万円超 | |
|---|---|---|
| 税務調査を受けた後の申告 | 15% | 20% |
| 事前通知の後の申告 | 10% | 15% |
なお期限後であっても、税務署からの通知前に自主的に申告すれば、無申告加算税は5%になります。
今回の改定では、「社会通念に照らして申告義務を認識していなかったとは言い難い規模の高額無申告」のペナルティを引き上げることになりました。
その金額は300万円を超える金額とされ、無申告加算税は10%加重で30%となります。
| 50万円まで | 50~300万円 | 300万円超 | |
|---|---|---|---|
| 税務調査を受けた後の申告 | 15% | 20% | 30% |
| 事前通知の後の申告 | 10% | 15% | 25% |
改正内容は、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。
悪質な無申告常習者への罰則
一定期間無申告を続けている「悪質な無申告常習者」に対して、罰則が強化されます。対象になるのは、前年度及び前々年度の国税について、無申告加算税又は重加算税(無
申告)を課される者が行う更なる無申告行為です。
恐らくこのケースに該当するのは、数年にわたり所得を申告していなかった者が、税務調査で数年分一度に期限後申告するパターンが多いでしょう。
この場合は、無申告を指摘された3年目以降の無申告加算税又は重加算税に10%加重されます。
無申告加算税については、令和4年分以前については先ほどの(従来の無申告加算税)、令和5年分以降については(改正後の無申告加算税)の税率に10%加重されます。
また過少申告加算税などが課税される場合で、仮装・隠ぺいにより申告している場合に課される重加算税は、40%に10%加重されるので50%の税率です。
無申告になってしまった(なりそうな)ときの対策
確定申告を忘れていたような場合、それに気が付いたとしたらどうすればよいのでしょうか?
あらかじめ言っておくと、無申告になっていることに気づいていなければ、いきなりやってくる税務署からの問い合わせや調査依頼で知ることになります。
これらの場合を含め、無申告になってしまった、あるいは無申告になりそうな対策を考えてみましょう。
まずはすみやかな期限後申告を
無申告によるペナルティを一番軽減できるのは、税務署から指摘される前に一刻も早く申告することです。期限後申告であることは同じでも、税額の負担を軽減できます。
この場合の無申告加算税は5%になるので、税額が多い方ほど負担が軽くなります。
また期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。
- その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。
- その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
- その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
ここでポイントになるのは2つ目の期限内納付で、分かりやすくいえば「3月15日までに申告していないことに気が付いた方」だけが、かかるだろう税額を仮に納付することで加算税を回避できます。

特別な事情がある場合
災害などのやむを得ない理由があるため、確定申告や所得税の納付が期限内にできない場合は、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を、納税地を所轄する税務署に提出しましょう。
確定申告を延長できる期間は、原則やむを得ない理由が解決してから2ヶ月以内ですが、税務署から個別指定されます。
相続財産で話がまとまっていないときは?
無申告で指摘されることが多いのが相続税で、調査を受けたときの追徴税額が大きくなる特徴があります。
その多くは「相続税への理解不足」であることが多く、「小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減の特例」などについてうろ覚えの知識で安心していた結果、想像外の税額負担となってしまうようです。
ある程度の相続財産がある場合は、税理士などの専門家に一度だけでも相談するのが無難ですが、申告期限(相続が開始された日から10ヶ月以内)までに遺産分割が揉めて協議がまとまっていないときはどうすればよいのでしょうか?
このようなケースでも申告期限が延びることはないので、各相続人などが民法に規定する相続分または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。
この場合は、「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の特例」が適用されないので、あとで特例を受けるために「申告期限後3年以内の分割見込書」を作成し、当初の相続税申告書とともに期限内に提出しましょう。
そうすることで、申告期限後3年以内に限り特例を適用することができます。
まとめ
日本は納税者が自主的に確定申告と納税を行うことが前提になっていますが、制度への理解不足などで無申告が増加しているようです。
実際に確定申告が必要なのか迷うことが多いのが現実ですが、知らなかったという言い訳は通用しません。
少しでも「利益があったかも」と思えるなら、確定申告の可能性を考えてみましょう。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
最近の投稿
- 2024.06.24
- 無申告で税務調査が入ったらどうなる?立ち合いを税理士に依頼すべきか、メリットを解説。
- 2024.06.20
- 【事業者必見】インボイスを税理士に相談・依頼するメリット5選!
- 2024.05.24
- 【税制改正 2024年】マンションの相続税評価の改正に伴い節税対策への影響とは?
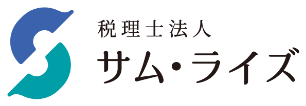
 0800-800-3602
0800-800-3602 お問い合わせ
お問い合わせ アクセス
アクセス