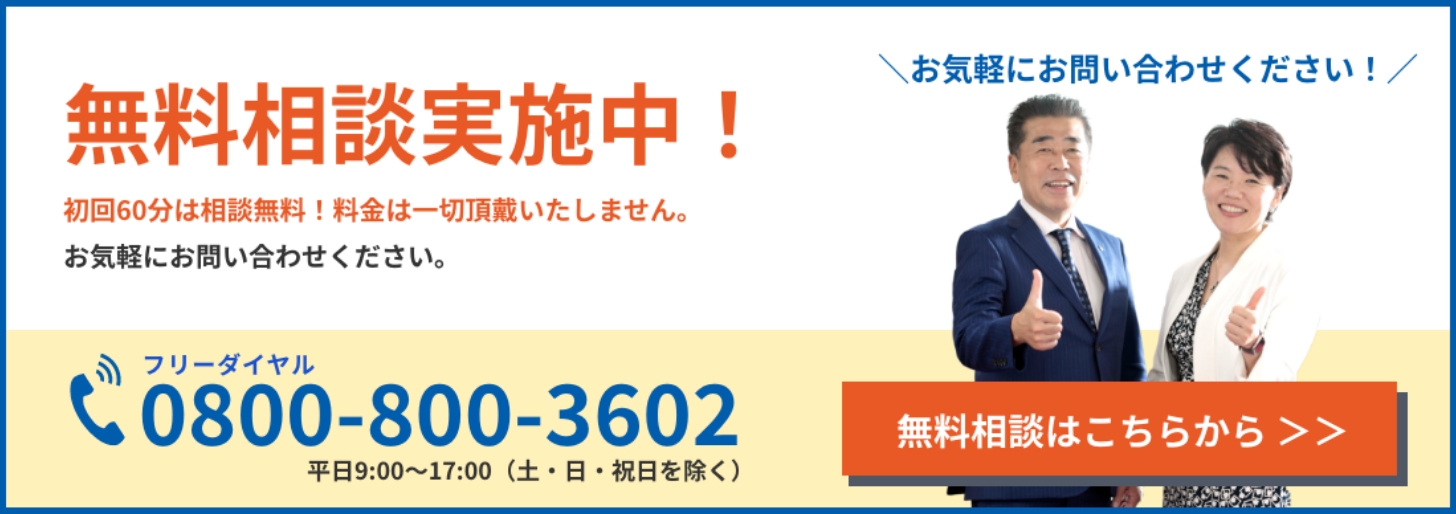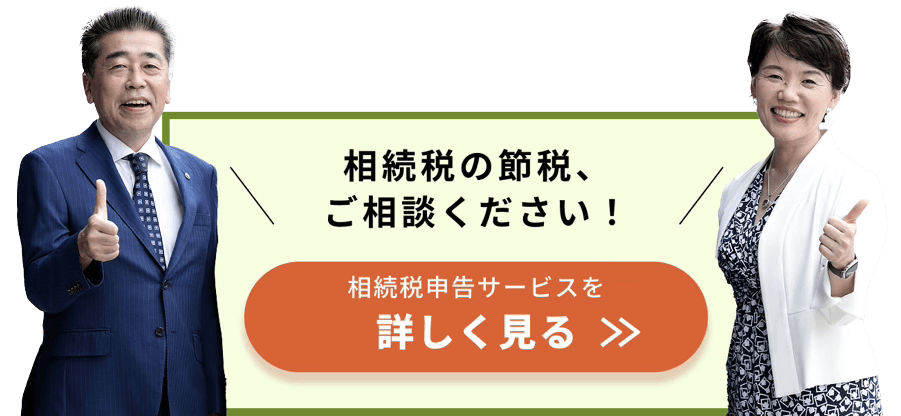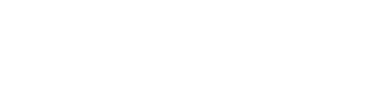「相続税の税務調査」に入られやすい人の特徴5つ|調査が入る「確率」「時期・頻度」、税務調査が入ると「どうなるか」も併せて解説
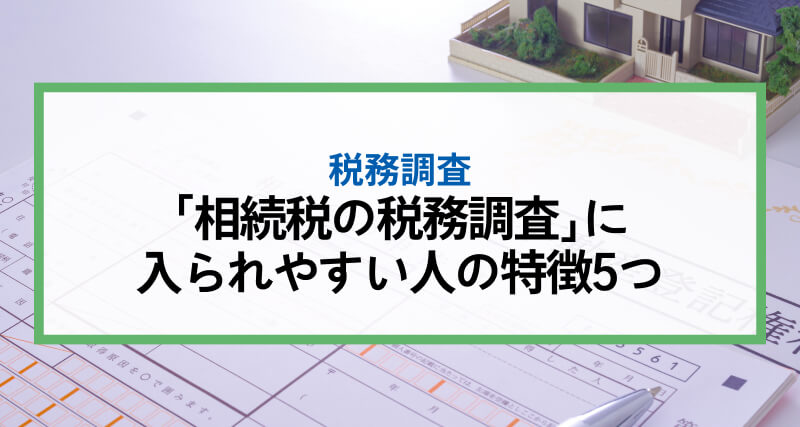
目次
本記事では、税務署による「相続税の税務調査」に入られるのかどうかと不安を持つ人向けに、「相続税の税務調査に入られやすい人の特徴」について詳しく解説しています。
「相続税の税務調査に入られやすい人」の特徴は、以下のとおりです。
「相続税の税務調査に入られやすい人」の特徴5つ
- 相続税がかかるのに申告をしていない(無申告)
- 相続財産の総額が大きい
- 相続財産のうち、「預貯金」の内訳が多い
- 「名義預金」が多くある
- 被相続人の資産が多い
1.「相続税」の税務調査について
「相続税」の税務調査について、以下の3つの項目に分けて簡単に解説します。
- 税務調査が入る確率
- 税務調査が入る「時期」や「頻度」
- 税務調査が入るとどうなるか
相続税の税務調査が入る確率
相続税の税務調査がくる確率は、約5.4%です。
税務調査が入る確率について、より詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
相続税の税務調査が入る「時期」や「頻度」
相続税の税務調査が入る時期は、
相続税の申告書を提出した1~2年後の8~11月頃が多いです。
また、相続税の税務調査が入る頻度は、
5年以内に1回あるかないかです。
ただし、上記以外の時期に調査される場合や、3年後以降に連絡がある場合もあります。
申告から2年を過ぎても調査の連絡がなければ、税務調査が入る可能性はかなり低くなるでしょう。
税務調査が入りやすい時期や頻度について、より詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
相続税の税務調査が入るとどうなるか
相続税の税務調査で、「申告漏れ」が発覚すると、
「過少申告税」や「延滞税」が課され、平均で約859万円の追徴税額を徴収されています。
令和5年(2023年)において、相続税の税務調査に入られた人8,556件のうち、相続税の申告漏れを指摘された人の数は7,200件で、「相続税の税務調査に入られた人の約84%」が申告漏れを指摘されています。
2.相続税の税務調査に入られやすい人の特徴
相続税の税務調査に入られやすい人の特徴は、以下のとおりです。
相続税の税務調査に入られやすい人の特徴5つ
- 相続税がかかるのに申告をしていない(無申告)
- 相続財産の総額が大きい
- 相続財産のうち、「預貯金」の内訳が多い
- 「名義預金」が多くある
- 被相続人の資産が多い
以下より詳しく解説します。
特徴①:相続税がかかるのに申告をしていない(無申告)
死亡届を出すと税務署に連絡されるため、相続したことを隠すことはできません。
特例を利用すると相続税がかからなくなる場合もありますが、申告書を提出していなければ確定申告をしていない(無申告)ことになります。
特徴②:相続財産の総額が大きい
相続税申告をする方の相続財産総額の全国平均は2億5,000万円程度といわれており、遺産総額が3億円を超えてくると税務調査に入られる可能性が高くなるでしょう。
相続財産の金額が大きくなると財産評価や税額計算のミスが起こりやすくなり、ミスがあったときの追徴税額が大きくなるからです。
特徴③:相続財産のうち、「預貯金」の内訳が多い
「預貯金」は不動産などの相続財産と比べると、金額がはっきりしているため、申告漏れを見つけやすく、税務調査対象となりやすいです。
また、相続の直前に預金の出入りが多い場合も、相続税を少なくするために財産を移したと疑われるため、税務調査に入られる可能性が高くなります。
特徴④:「名義預金」が多くある
「名義預金」とは、亡くなった人が家族名義で作った口座のことです。
実際に管理していたのが、名義人なら相続財産とみなされ、相続税の対象になります。
収入が少ないはずである「専業主婦」や「孫」などの預貯金が多ければ、「名義預金」ではないかと疑われて税務調査が入られやすくなります。
特徴⑤:被相続人の資産が多い
被相続人自身の口座であっても、収入に比べて預金が多いと、「生前贈与」の疑いで税務調査に入られやすくなります。
税理士法人サム・ライズは、相続税申告の経験が豊富な税理士事務所です。
さまざまな専門家の意見を参考にしながら、土地の評価額を下げる工夫や、生命保険の有効活用、賃貸物件の建築、そもそも相続財産に該当するかどうかの見極めなど、さまざまな方法を使って相続税の節税を図っていきます!
3.相続税の税務調査に備えて行うべき4つの対策
相続税の税務調査に備えて行うべき対策は、以下のとおりです。
相続税の税務調査に備えて行うべき4つの対策
- 申告に漏れやミスがないかを確認する
- 被相続人の財産は事前に把握しておく
- 相続に関するやり取りはすべて残しておく
- 税理士に相談する
以下より詳しく解説します。
対策①:申告に漏れやミスがないかを確認する
相続税の税務調査で、追徴課税を徴収されないために最も重要なことは、相続税の申告に漏れやミスがないかを確認して正しく申告することです。
相続財産の見落としがないようにすべての財産を調べたうえ、計算ミスがないか、複数回確認しましょう。
対策②:被相続人の財産は事前に把握しておく
相続税の申告漏れは、相続財産を正確に把握していないために起こることもあります。
したがって、亡くなる前から事前に被相続人の財産を把握しておく必要があるといえます。
ただし、実際に家族が財産を調べるのは限度があるため、被相続人に対して、「財産目録」を作ってもらうように働きかけましょう。
対策③:相続に関するやり取りはすべて残しておく
相続に関するやり取りを、後からでも見られるように、すべて記録して残しておくことも大切です。
遺産を分割する際に、誰がどの遺産を相続するかについては遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議によって相続人それぞれが納める相続税額が決まるため、遺産分割協議書があれば、正しく納税していることを証明できます。
対策④:税理士に相談する
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
最近の投稿
- 2025.08.14
- リーダーシップへの舞台裏Vol.22 ~今を駆ける社長のインタビューシリーズ~
- 2025.08.14
- リーダーシップへの舞台裏Vol.21 ~今を駆ける社長のインタビューシリーズ~
- 2025.07.31
- 税理士に無申告解消を依頼した事例 「税務調査が入った」編
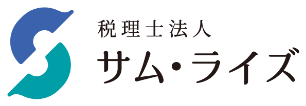
 0800-800-3602
0800-800-3602 お問い合わせ
お問い合わせ アクセス
アクセス