相続 遺留分とは?相続人の権利と税務上の考慮点を税理士が解説

目次
相続における遺留分とは、相続人に最低限度保障される「相続財産を受取ることができる権利」です。
遺留分を主張する相手は、不公平な遺産分割が行われたときに遺言等によって多く財産を相続した人に対してですが、意外と権利を知らずにいる方も見られます。
この記事では、相続財産が少なくてもあり得るトラブルと遺留分の関係、そして遺留分の権利行使が相続税に与える影響について税理士が分かりやすく解説します。
遺留分の仕組みと揉めた場合の解決方法
相続には、被相続人(故人)と被相続人の双方が必ずしも納得できないケースがあり、トラブル時によく聞かれるのが遺留分という相続人の権利です。
相続トラブルと聞けば、たくさん財産を持っている被相続人だけのものだと思いがちですが、意外と誰にでも起こり得ます。
まずは遺留分の仕組みを理解し、その権利を行使するようなケースについて考えてみましょう。
不公平な遺産分割になるケース
相続というと何となく民法で定められた法定相続分をイメージしますが、遺言を残すようなケースでは法定相続分とは違う相続を指定されることが多いようです。
それが相続人全員納得できるものであれば問題はないのですが、一部のケースでは法定相続すら無視して、「次男に全てを遺贈する」といった遺言もあります。
遺言は被相続人が自身の死後の財産分割について、自分の意志を示す重要な書面なので、このような極端な事例もあるわけです。
相続人から見て不公平なものは、遺言による遺産分割だけではなく、極端な生前贈与もそれに該当します。
被相続人が亡くなり、調べてみたらほとんどの財産が特定の相続人に権利移転されていたようなケースがこれに当たります。
現代の遺留分制度は、このような特定の相続人または個人に財産を集中させようとする意思を制限する機能をもっています。
遺留分が認められる相続人の範囲
遺留分が認められるのは、相続人であることは当然として、その範囲から被相続人の兄弟姉妹は除かれます。
なぜ遺留分から兄弟姉妹が外されているかといえば、この遺留分制度の成り立ちを考えれば理解できるでしょう。
実は遺留分制度は、明治民法により定められたもので、元来の目的は「家の当主が、本家以外の個人へ散財することを防ぐため」だったのです。
今では「家督を継ぐ」などという制度は無くなりましたが、遺留分制度の中身はほぼそのまま維持されていて、そのため遺留分の権利は配偶者、直系卑属、直系尊属だけに限られています。
遺留分の割合と計算方法
遺留分とは、最低限度保障される「遺産の取り分」なわけですが、その最低限とはどのくらいの割合なのでしょうか。
遺留分の計算は、2つのステップで進めていきますが、最初に「全体でどのくらいの遺留分が認められるか」を計算します。
これを「総体的遺留分」といい、誰が相続人になるのかによって異なり、以下のいずれかです。
- 親などの直系尊属のみが相続人の場合 ・・・ この場合の総体的遺留分は遺産全体の3分の1です。
- その他の場合 ・・・ 相続人に配偶者や直系卑属(子や孫など)が含まれる場合は、遺産全体の2分の1が総体的遺留分になります。
総体的遺留分が計算できたら、個別的遺留分(個々人の受け取れる権利)を計算するのですが、簡単いえば「法定相続分の半分」の割合となります。
例えば妻(配偶者)と子が2人いる被相続人が、「愛人に全財産を相続する」という遺言書を残していた場合、妻と子は遺留分の権利を主張することができます。
「できます」というのは、必ずしもこの権利を行使する必要はなく、遺留分は放棄することもできるのです。
妻と子2人というこのケースでは、総体的遺留分は「その他の場合」になるので遺産全体の2分の1となります。
そして個別的遺留分は、妻が法定相続分の半分(1/2×半分=1/4)となり、子はそれぞれ(1/2×半分÷2人=1/8)です。

遺留分を侵害されたときの対処方法
遺留分を侵害されたら、つまり法定相続人でありながら遺残が全く受取れない、もしくは遺留分未満しか受け取れないような場合、侵害した相手に「遺留分侵害額請求」を行います。
遺留分侵害額請求は、「侵害された遺留分をお金で払ってもらう手続き」で、2019年7月1日に施行された改正相続法で変更された手続きです。
それ以前の「遺留分減殺請求権」では、遺留分をお金ではなく遺産そのものを取り戻す権利でした。
もし相続財産が土地しかなかった場合、先ほどの「愛人へ100%相続」するケースでは、愛人と遺留分を主張する妻と子2人が、土地を共有する状態になってしまいます。
こうなると先の解決が難しかったのが、相続で揉めやすい「不動産の共有」を回避できるようになりました。
実は相続財産が不動産しかなく、相続人が共有となった不動産にまつわるトラブルは非常に多く、代を重ねるごとに解決が困難になるものです。
これが「お金で解決できる権利」に変わったことで、使い勝手の良い制度に変わったといえます。
遺留分侵害額請求の流れ
遺留分侵害額請求を行うときは、以下の順で検討することになりますが、遺留分を巡る交渉はトラブルが絡むことが多いものです。
最初に話し合いでの解決を図ることになりますが、できれば弁護士などに依頼して進めた方が良いでしょう。
- 遺留分を侵害した相手と協議する ・・・ 遺留分を侵害した相手が親族など、話し合えるのであれば協議して解決することが良いでしょう。ただ「侵害した」といっても、相手にはそんな意志がない場合もあるので、冷静に話し合うことが重要です。そもそも関係が良好でない相手と協議するなら、やはり弁護士の力を借りることがオススメです。
- 家庭裁判所で遺留分調停を申し立てる ・・・ 話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所で遺留分調停を申し立てましょう。遺留分調停とは、遺留分権利者と侵害者とが、裁判官・調停委員を介した話合いにより紛争を解決する手続です。相手と顔を合わさず話し合いができるメリットもありますが、合意ができたら調停が成立して調停調書が作成されます。
- 遺留分侵害額請求訴訟 ・・・ 遺留分調停でも合意できないときは、遺留分侵害額請求訴訟を起こさなければなりません。この場合、遺留分侵害額請求の金額が140万円以内であれば簡易裁判所、140万円以上の場合には地方裁判所に対して訴訟提起することになります。当然手続なども面倒になり、場合によっては解決まで長期化することになります。
遺留分侵害額請求の流れを見れば理解できると思いますが、早い段階で合意できなければどんどん解決が難しくなってしまいます。お金の絡むことは、それまで良好だった親族関係にも良い影響はないので、やはり早い段階から相続問題に強い弁護士に依頼するほうが無難です。
遺留分の時効
遺留分侵害額請求権には時効が適用されるので、注意しなければ請求権自体を失ってしまいます。
民法1048条には、「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」とあります。
つまり遺贈分を侵害する贈与・遺贈のあることを知った日から、1年間何もしなければ時効が成立する可能性が極めて高くなります。
また相続開始の日から10年を経過すると、時効を止める方法はなくなるので、遺留分の権利を行使するためには早めの行動が大切です。
遺留分侵害額請求と相続税の申告
相続によって一定以上の相続財産がある場合には、相続税の申告と納付が必要になります。
相続税の計算は、相続税の総額を計算した後に、実際の遺産相続額に応じて税額を按分するのですが、遺留分侵害額請求をすることでどのような影響があるのでしょうか。
遺留分侵害額請求をすると、請求者の相続額が増えることになるので、税額も変わってくることは理解できると思います。
では実際の影響について、いくつかのケースごとに確認してみましょう。
相続税申告前の場合
相続税の申告・納付期限は、相続開始の日から10ヶ月以内ですが、それまでに遺留分の請求について合意できている場合は、合意後の金額をもって相続税の申告をするだけです。
言うまでもありませんが、そもそも相続財産が相続税の基礎控除内に収まるような場合は、取り分が変わろうが相続税とは関係ありません。
相続税申告後に遺留分を受取った場合
相続税申告後に遺留分の精算が完了したケースは、本来であれば遺留分を侵害した側(遺留分義務者)の相続税額は減り、遺留分を貰った側(遺留分権利者)の相続税額が増えることになります。
このとき遺留分義務者が、納める税金が多すぎた場合や還付される税金が少なすぎた場合に、これらの金額を正しい額に訂正するための「更正の請求」をするかしないかで、対応が異なります。
遺留分義務者が更正の請求をした場合、遺留分権利者は修正申告または期限後申告をしなければなりません。
つまり増えた相続税額を改めて納付することになる、または新たに納税義務者になることになります。
もし遺留分義務者が更正の請求をしなかったときは、遺留分権利者はなにもする必要はありません。
これは遺留分権利者が払うべき相続税を、遺留分義務者が支払っている状態なので、税務署側が問題にしないためです。
申告期限までに決着しなかった場合
遺留分侵害額請求の決着がついていない状態で申告期限がきたときは、遺留分精算前の遺産相続内容に従って暫定的に相続税申告を行います。
つまり遺言に書かれている分割内容など、仮の状態でも申告を行い、遺留分請求が確定した段階で更正の請求や修正申告で対応しましょう。
なお通常であれば修正申告や期限後申告をすると、延滞税や加算税などのペナルティが発生しますが、「遺留分額が確定した日の翌日から4カ月以内」に修正申告や期限後申告をすれば、これらのペナルティは免除されます。

まとめ
相続は、被相続人と相続人の全てが納得できる円満な内容であれば、相続税の申告や納税だけを心配すれば事足りるものです。
しかし遺産分割で問題があると、途端に手続きや交渉などのハードルが一気に上がってしまいます。
このような失敗を避けるためには、相続税の申告が必要なのかどうかを含めて、一度相続に強い税理士に相談することがオススメです。
もし遺産分割協議や遺留分の問題がありそうなら、必要に応じて弁護士の紹介も受けられるので、不安のほとんどは解決できるでしょう。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
最近の投稿
- 2026.02.27
- 税務調査で税理士の立ち会いが「ある場合とない場合」の違いとメリット
- 2026.02.27
- 相続税申告の税理士「費用」は遺産総額の0.5%~1.5%が相場
- 2026.02.27
- 5,000万円相続時の「税金&諸費用」 例|埼玉県川越市 60代の依頼主の場合
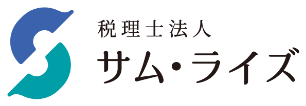
 0800-800-3602
0800-800-3602 お問い合わせ
お問い合わせ アクセス
アクセス


