相続税は財産がいくらから発生する?基礎知識と申告の注意点を税理士が解説

目次
亡くなった方から財産を相続したときに発生する相続税は、相続財産の評価額が一定額を超えると課税されます。
令和3年のデータでは、死亡者数に対する相続税の課税件数の割合は9.3%となっており、意外と多いと思わないでしょうか。
本記事では、相続税は財産がいくらから発生するのかなど、相続税の基礎知識と申告の注意点について税理士が解説します。
相続税の基礎控除と3,600万円
相続税がいくらから発生するのかネットなどを調べると、よく「3,600万円」という金額を見かけます。
これは相続税で「ここまでは相続税は課税しません」という基礎控除の最低額で、相続財産の課税評価額が基礎控除を下回れば、相続税の申告も必要ありません。
まずは相続税の基礎控除の計算方法や、その際の注意点について説明します。
基礎控除の計算方法
相続税の基礎控除額は、以下の計算式によって求められた金額です。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
つまり法定相続人が1人だったとした場合、その基礎控除額は3,600万円ということになります。
法定相続人の数が多いほど基礎控除額は増えるのですが、相続税に関しては有利だとしても相続財産の取り分は少なくなるので、決して得したとはいえないでしょう。
法定相続人になる人
法定相続人とは、民法によって定められた被相続人(亡くなった方)の財産を相続できる人です。
もちろん法定相続人以外に財産を相続させることはできますが、相続税の基礎控除額の計算は法定相続人を基に計算されます。
法定相続人になる人は、被相続人の配偶者と被相続人の血族で、血族相続人には下記のように相続順位が定められています。
- 第1順位 子ども、代襲相続人(直系卑属)
- 第2順位 親、祖父母(直系尊属)
- 第3順位 兄弟姉妹、代襲相続人(傍系血族)
法定相続人が配偶者や子どもである場合は難しいことはないのですが、配偶者も子ども(孫)もおらず、その他の順位の相続人となると「法定相続人は何人いるのか?」という確認作業の難易度は上がります。
また離婚した配偶者との間に生まれた子どもは、第1順位の法定相続人となります。
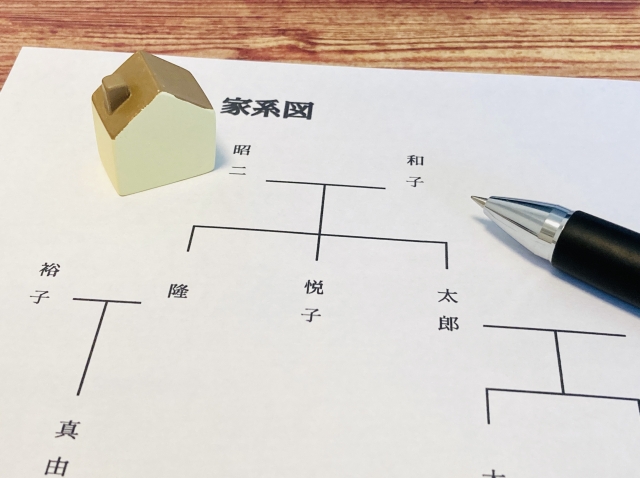
基礎控除の計算の注意点
法定相続人の数が確定したら、先ほどの計算式で基礎控除額を計算します。このとき法定相続人のなかに「相続放棄」したものがいたとしても、基礎控除額の計算上、相続放棄はなかったものとして扱います。
相続時精算課税制度の見直し
「相続時精算課税制度」は、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子や孫に対して財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。
この制度を利用すると、累計で2,500万円の特別控除額まで贈与税はかかりませんが、相続発生時には、相続財産に加算され相続税の対象となります。
生前にまとまったお金を非課税で贈与するための制度ですが、いったん選択すると以降の贈与は少額でも申告が必要となるなど、少し使い勝手の悪い制度でした。
また相続税対策としても、暦年課税制度にある基礎控除や相続財産への加算期間の制限に相当する規定が存在しないので利用のメリットが感じられませんでした。
それが今回の改正では、暦年課税の基礎控除とは別途110万円の基礎控除を創設され、しかも毎年基礎控除内の贈与であれば申告が不要になりました。
つまり相続時精算課税制度の特別控除(2,500万円)とは別に、毎年110万円の基礎控除が受けられるので、相続税対策としても使いやすい制度になったといえます。
また、この制度を利用して土地または建物の贈与を受けた場合、その土地や建物が災害により一定の被害を受けたときは、相続税の計算において評価額を再計算することができるようになりました。
これらの改正は、2024年1月1日以降に適用されます。
ミスは許されない?相続財産の計算
基礎控除額が分かったら、あとは相続財産の課税評価額がそれを上回るか下回るかが問題となります。
実は、相続税の申告で難しいのが相続財産の洗い出しとその評価で、一般の方には馴染みの薄い工程です。
相続税が課税されそうなら、早い段階で税理士などの専門家に依頼することをオススメしますが、ここでは相続財産についての基本を説明します。
相続財産に含まれる資産
相続税がかかる財産ですが、国税庁のホームページを見ると「現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの」とされています。
つまり、言葉は悪いのですが「金目のもの全部」ということです。
ただ仮想通貨を除くデジタル資産やトレーティングカードなど、経済的価値があっても相続税における取扱いが明示されていないものもあるので、疑問に感じたことは税理士などの専門家に相談しましょう。
なお以下の財産には相続税は課税されません。
- 墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など
- 悔みとして支給される弔慰金や花輪代
- 慰謝料としての損害賠償金(逸失利益の補償は課税されます)
相続財産から控除できる負債や費用
相続される財産はプラスのものだけとは限らす、借入金やローンなど負債も含まれ、これらはマイナスの相続財産として差引されます。
また被相続人の葬儀にかかった費用も相続財産から控除できますが、次のような費用は遺産総額から差し引く葬式費用には該当しないので注意しましょう。
- 香典返しのためにかかった費用
- 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
- 初七日や法事などのためにかかった費用
ただ、被相続人の49日に行った「偲ぶ会」が葬儀費用にあたるか争われた国税不服審判所の審査請求で、葬儀費用に当たると認定された判断もあります。
みなし相続財産をチェック
本来は相続財産ではないものの、相続税で相続財産とされるのが「みなし相続財産」です。
みなし相続財産で代表的なものは、「死亡保険金」と「死亡退職金」ですが、それぞれ条件や控除額が決められています。
死亡保険金のうち、みなし相続財産とされるのは被相続人がその保険料の全部又は一部を負担していたものです。
もし死亡保険金を受け取った場合は、被保険者と契約者(保険料を支払っていた人)の関係を確認することが大事になります。
死亡退職金は、本来被相続人が勤務先等から受け取るはずの退職金だったことから、みなし相続財産になります。
みなし相続財産とされる退職金は、「死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの」、または「生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの」のいずれかです。
なお被相続人が死亡して3年を過ぎてから支給される死亡退職金は、受取人の一時所得として所得税が課税されます。
みなし相続財産とされる死亡保険金と死亡退職金は、それぞれ以下の非課税枠が設けられています。
みなし相続財産の非課税枠=500万円×法定相続人の数
相続時精算課税を選択している場合
贈与を行っても2,500万円までの非課税枠がある相続時精算課税制度を選択すると、それまでに贈与した財産はすべて相続財産に加算して相続税の計算を行います。
この贈与額を相続財産に参入漏れがないように注意しましょう。
令和5年税制改正では、相続時精算課税制度の利用促進のため、現行の特別控除2,500万円とは別に基礎控除110万円が新設されました。
令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されますが、利用する方が増えることが予想されるので、より注意が必要です。
亡前3~7年の贈与財産
死亡前に多額の贈与をすることで相続税の課税を免れることを防ぐため、被相続人の死亡前3年以内に、被相続人から贈与された財産価額は、相続財産の価額に加算して相続税の計算をします。
この価額を「持ち戻し」といいますが、令和5年税制改正で持ち戻しの期間が3年から7年に拡大され、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。
ただ新たに拡大された4年間の贈与については、合計100万円の非課税枠が設けられました。
小規模宅地等の特例
被相続人が自宅または事業のために使用していた宅地を相続する場合、小規模宅地等の特例で宅地の評価額を最大80%減額することができますが、これは相続税の申告を期限内にした場合のみ適用されます。
つまり特例を使えば相続財産の価額が基礎控除内に収まるとしても、期限後申告あるいは無申告だと特例は使えません。
小規模宅地等の特例は適用要件も複雑なので、該当しそうな場合は専門家へ相談しましょう。

相続財産が基礎控除を超えた場合の注意点
相続財産が基礎控除額を上回ったからといって、必ず相続税が課税されるわけではありません。
それは、配偶者の税額軽減措置や、未成年者控除・障害者控除などがあるからです。
税額がゼロになるからといって、相続税の申告をしなくてよいわけではありません。
配偶者の税額控除とその注意点
相続税の配偶者控除とは、故人の配偶者の生活を守るためのもので、具体的には配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となるものが1億6千万円までであれば相続税が課税されない制度です。
また1億6千万円を超えたとしても、配偶者の相続財産が法定相続分以内であれば相続税は課税されません。
相続税の配偶者控除を受けるための要件は以下のとおりです。
- 戸籍上の配偶者であること
- 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
- 相続税の申告書を税務署に提出すること
見て分かるとおり、相続税の申告書を提出することが適用要件なので、相続人が配偶者一人で遺産が1億6千万円以内だとしてもしんおくが必要です。
ただ小規模宅地等の特例とは違い、申告期限を過ぎたとしても適用されますが、税務調査が入るなど指摘を受けてからでは、配偶者控除は受けることができなくなる可能性があります。
また申告期限愛に遺産分割が完了しない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付することで、遺産分割協議を延長することが可能です。
この配偶者控除は節税効果が大きいのですが使い過ぎてしまうと、相続を受けた配偶者が亡くなることで発生する二次相続時に多額の相続税がかかることがあります。
相続税の有無はともかく、二次相続は必ず発生することなので、そこまで見越した遺産分割を考えることも必要です。
まとめ
相続税についていくらから発生するのかを中心に解説してきました。相続税の申告は、相続発生の日から10ヶ月以内に行わなければならず、意外と余裕のないものです。
明らかに基礎控除額以内の相続財産しかない場合は安心ですが、少しでも不安を覚えるなら税理士に相談することをオススメします。
また相続が発生する前に相談しておけば、税負担を軽くするための対策も行うことができます。
どちらの場合にしても、早めの行動が無駄な相続税を払わないための近道です。
税理士法人サム・ライズ
代表税理士。
大原簿記学校法人税税法課専任講師を得て平成5年12月税理士試験合格、平成8年1月林税理士事務所を開業、平成16年12月税理士法人サム・ライズを設立。
税理士法人サム・ライズは、税理士顧問・創業支援・相続税・資金調達・無申告・税務調査立ち合い・クラウド会計・社会福祉法人など数多くのサービスで中小企業の皆様をサポートいたします。
最近の投稿
- 2026.02.27
- 税務調査で税理士の立ち会いが「ある場合とない場合」の違いとメリット
- 2026.02.27
- 相続税申告の税理士「費用」は遺産総額の0.5%~1.5%が相場
- 2026.02.27
- 5,000万円相続時の「税金&諸費用」 例|埼玉県川越市 60代の依頼主の場合
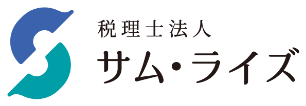
 0800-800-3602
0800-800-3602 お問い合わせ
お問い合わせ アクセス
アクセス


