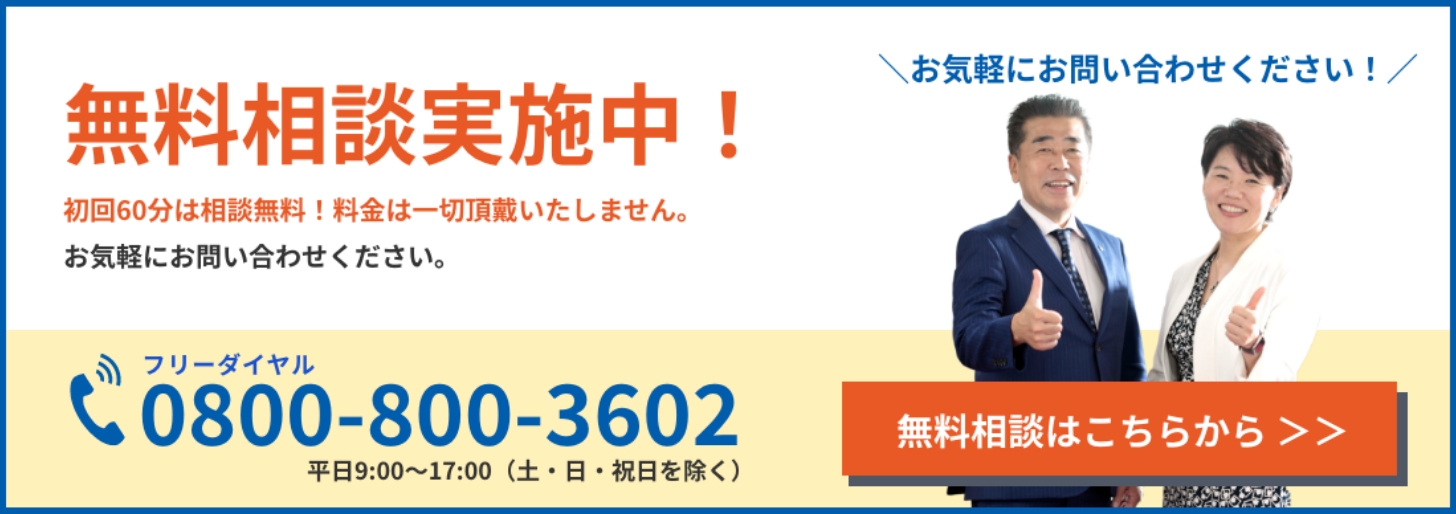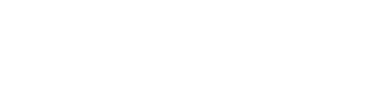リーダーシップへの舞台裏Vol.11 ~今を駆ける社長のインタビューシリーズ~

目次
やるからには人より少し上手にやる。
やっているうちに仕事は楽しくなる
来年、創立50周年を迎える増美保育園の理事長をされている鈴木晶夫先生。川越市内に認可保育園3園と分園を2園運営なさっています。温和で優しい鈴木理事長は、そのお人柄で園児・保護者はもちろん、同業の保育関係者からも絶大な信頼を得ています。今回は鈴木理事長の保育へのこだわりと大切にしているポリシーを伺いました。
【プロフィール】
昭和35年に浦和市(現さいたま市)生まれ。
小学校4年生からサッカーを始め、6年生の時に浦和市の大会にて優勝、中学3年生では県大会優勝と好成績を収め、大学生までサッカーを続ける。
来年、創立50周年を迎える増美保育園の理事長をされている鈴木晶夫先生。川越市内に認可保育園3園と分園を2園運営なさっています。温和で優しい鈴木理事長は、そのお人柄で園児・保護者はもちろん、同業の保育関係者からも絶大な信頼を得ています。今回は鈴木理事長の保育へのこだわりと大切にしているポリシーを伺いました。
大学卒業後、ファッションビルのコンサルタント会社に勤め、結婚を機に川越市へ転居。同時期に転職をし、不動産販売事業に従事する。その後、グループ企業である社会福祉法人 川越福祉会 増美保育園の施設長に就任する。現在は同会の理事長として、地域に愛される保育園の運営に力を注いでいる。
趣味は釣り(年2回北海道へ)、鮨屋・てんぷら屋などの日本料理店めぐり、東京の街歩き、地方の教会建築を観ること、愛犬と遊ぶこと。
園長そして理事長になったのは
成り行きと神頼み?!ご縁がつないだ経歴
林:鈴木理事長、今日はとても楽しみにしておりました。よろしくお願いします! 25年近く前に息子を預かってもらってからのご縁なので、先生のことは良く存じ上げておりますが、あらためて会社名と事業の概要をお話しいただけますか。
鈴木:今日はどうぞよろしくお願いします。私どもの法人は社会福祉法人 川越福祉会と申しまして、現在、川越市内に認可保育園を3園と分園2園を運営しております。先生のご子息をお預かりした頃はちょうど私が園長(施設長)になったばかりのころでしたので、かれこれ25年近くになりますね。園自体は来年で創立 50周年を迎えます。
林:本当に素晴らしい保育園で、先生には感謝しかありません。まずは、先生がこれまでの経歴を経て保育園のお仕事に就かれる事になった経緯を伺ってもよろしいですか。
鈴木:大学を出て、最初についた仕事は、
1つのファッションビルの中に色んなブランドを入れる「テナントミキシング」と言われる仕事でした。その会社をやめる時に、ちょうど奥さん(現施設長)と結婚することになりまして…。いわば無職のような状態での結婚ですから、今思えば思い切ったことをしたなぁと思います。先代である義理の父は川越で増田建設という建設会社を経営していたのですが、先代から、うちの家業を手伝わないか、と声をかけていただき住宅販売の営業を10年ほどやらせていただきました。
林:そうだったんですね!
鈴木::その後、また先代から「今度は保育園をやって」と言われて、次の週には保育園に勤務していました。振り返ってみると、ここまでの仕事の中で、自分で決めたのは最初のテナントミキシングの仕事くらいで、あとは他の人が私の仕事を決めているんですよね。
林:わー!先生柔軟!
鈴木:柔軟というか、特に希望がなかったんです。普通、社長さんってこういうことをやりたい!みたいな思いがあって、独立する方が多いと思います。僕はそういうこれをやりたいというのがあまり無くて、強いて言うならものづくりをしていくような仕事より、人と関わる仕事や人と触れ合ってお付き合いしていく仕事が好きだな、と思っていました。人と話をして、相手の想いにアプローチして、その想いに応えていくことはどんな仕事にも必要なことだと思っています。自分の中でいつも考えていたことは、どんな仕事にせよ、「人より少し上手くやりたい」ということでした。これはどんな事をしていても結構自分の中で根底にある想いかなと思います。

奥様のお父様から引き継いだ増美保育園も来年で創立50周年。この節目を迎えるに当たって、ご夫婦で乗り越えたものも相当あっただろうなぁと思うと、とても感慨深いです。
保育園はお父さん・お母さんの就労支援でもある、という考え方
林:住宅の代理店営業から、保育園の運営への転職って、全く違う仕事ですよね。戸惑うことも多かったのではないですか?
鈴木:そうですね、ただ、厚労省から出ているような、保育園におけるきまりごとなどは本などを読めば書いてあることなので、法律的な知識という点はあまり問題ではなかったです。人を相手にする、人と付き合っていくっていうところにおいては、これまでの仕事も保育の仕事も同じなんですよね。今までは住宅を作りたい人へアプローチ、保育園では、お子さんと、保護者の方、そして働いてくれている保育士さんへのアプローチ、ということで、その角度が増えただけで変わっていない、と思ったんです。
林:そう言われると確かにそうですね。
鈴木:ただ、これまでは住宅を作りたい人が相手でしたが、保育の現場では、お子さんと保護者、そして保育士という3つの視点になったというのはすこし大変な部分もありました。また、当時は男性の園長も少なかったので、これまでの男性社会と異なる面で色々苦労したところもありました。でも、どんな仕事でもやっていくうちに面白みを感じられますし、今度はこうしてみよう、と思うことが見えてくるので、とてもやりがいがありましたね。
林:さすがですね。先ほど、アプローチする先が増えただけとおっしゃいましたが保育園と住宅で一番違うなって思ったことはどんな事ですか?
鈴木:住宅だと、家を建てる人(決定者)と利益を受ける人は同一になるのですが、保育園だと、どこの保育園に行くか決めるのは、親御さんが決定者になるんですね。そして、利益を受ける(保育園行く)のはお子さんになります。なので、保護者の方々に、どんな保育をしているか、園の理念や教育方針などを丁寧に説明するということは欠かさず行ってきました。
林:私も増美保育園さんの方針にとても支えられた保護者の一人なので、先生の仰っていることが本当によくわかります。出張で遅くなった時も遅くまで見ていただいて、おむつも知らないうちに外れていました。働くお母さんにとって頼りになる保育園があるって、どれだけ心強いことか。増美保育園さんは保護者会や役員会がなくて、お遊戯会や運動会は親が手伝う事もなく、親たちはお客様のように子供の姿を観させてもらえるのですよね。行事の準備はとても大変だったと思います。影で支えてくださった先生たちには感謝でいっぱいです。小学校に行ってから、保護者がやることってこんなにあるんだ!と知って、あらためてありがたさがわかりました。
鈴木:僕は保育園って、お子さんの利益はもちろんそうですが、親御さんの就労支援でもあると思っているんです。つまり決定者である親御さんの最善の利益も考えるということです。それも私たちの仕事だと思っています。
林:先生はそれを25年前から一貫してやられているんですよね。私は先生がおっしゃった、「親御さんの仕事の就労支援も私たちの仕事だから」という言葉にどれだけ励まされたか…保育者の先生たちの教育にもとても熱心に取り組んでいらっしゃると感じます。

本当にたくさんある保育園の年間行事で、保護者が準備するものはほとんどありません。それなのに、子どもたちが着ている手作り衣装や、飾り付けのクオリティの高さはピカイチ。
親としては、園の心のこもった行事にお招きしてもらう感覚で、可愛い子どもがさらに何百倍にも可愛く見えていました!細部に渡る園や保育士さんたちの愛情を強く感じる瞬間でした。

職員研修の様子。姉妹園の職員が一堂に集まり、グループで課題について話し合うのだそう。それぞれの意見を出し合い、日々の保育の見直しと、より良い改善方法を職員自らが探ります。
参加の保育士さんは真剣そのもの。個々の「もっと良い保育とは?」という強い探究心が、保育士としての専門性と組織性を高めるそうです。
また、職員の家庭環境を優先的に考えるなど、鈴木理事長の愛情が保育士さんの日々の活動をいきいきとさせているのがよくわかります。
職員の先生たちに期待する「保育力」とは
鈴木:そうですね。私は保育士の先生に身につけて欲しいと思っているものが2つあります。1つが保育士としての専門性、そしてもう1つが組織性=“みんなでやる”という能力です。専門性は言うまでもなく保育士として学ぶべき知識なので、身につけてもらいたいと思っているのですが、保育園というのは、一人の保育士が一人の園児を見るのではなく、大勢のお子さんをみんなで見るので、この組織性という能力がとても重要な能力であると考えています。クラスの子をみるのも大事だけれど、園全体を見るというのも重要です。保育の専門学校ではおそらく組織性というようなことは教わってこなかったと思うので、年間に4~5回コーチングの先生を読んで勉強会をしたり、リーダー会議を通じてコミュニケーションを学ぶ場を設けたりして、組織性を養うための努力をしています
林:きっとその成果の現れだと思うのですが、増美保育園の先生方って、定着率がとても良いですよね。福祉の世界って平均的な定着率が3年と言われていますが、増美保育園さんは長く働いて下さる先生がとても多いと感じます。結婚して子どもを産んでも、育休後に戻られる先生方も多いですよね?その文化ってどうやって作ってこられたのですか?
鈴木:ええ、僕もどうしてだか分からないのですが(笑)。もしかすると、この園にいると自分の保育力(スキル)が上がると思ってもらっているのかなと。
林:保育力?
鈴木:今、色んなお子さんがいらっしゃいますよね。発達が心配なお子さん、肉体的に不自由な(ハンデがある)お子さんなど。僕は、どのような環境にいるお子さんであっても、別け隔てなくみんな一緒に保育したいという気持ちがあるんです。もちろん現場を預かる先生方は大変だとは思います。でも、そういうお子さんの保育に関わらせてもらうことで、目には見えない先生たちの保育力が高まっていると思います。もちろん、増美保育園自体の保育力も上がっていきます。この結果、新しい文化がうまれたり、ゆずりあったり、優しくしたり、個性を認めあったりということが起きて、子供たちの心が育っていくと思うんですね。ちょっとおこがましいかもしれませんが、どこでも保育士としてやっていける人を育てるという意味で、僕の仕事は士業だと思っています。
林:はい、私も同感です。先生のお仕事は誰にでも出来るようなお仕事ではないと私も思います。
鈴木:保育士の先生たちには、自分の保育力を高めて、どこに行っても働けるような保育士さんになって欲しいと思っています。僕は、保育士という仕事が女性に最も相応しい仕事だと思っているんです。女性は年齢が高くなることが就業の障害になる仕事が多い中、保育士という仕事は歳を重ねると味が出てくるじゃないですか(笑)。もちろん、ただやることをこなしているだけではその味は出ないと思うんですけどね。いろいろな経験をして、自分の引き出しを増やしてほしいと思います。引き出しは多ければ多いほどいいですからね。是非、増美保育園で保育力をつけて、どこでも通用する保育士さんになってほしいと思っています。

帰着するのは人と人との繋がり
~地域との関わりを大切に~
林:ありがとうございます。では最後に先生がこれからやっていきたいこと、将来の展望などをお伺いしてもよろしいですか。
鈴木:そうですね。仕事はいけるところまで行って、生涯現役でいたいなと思っています。若い人の迷惑にならないようにとは思っていますが(笑)。これからの展望としては、保育と隣接する部分をもう少し増やしていけたらなと思っています。ここは亜由美先生もよくご存じだと思いますが、福祉であっても数字が伴わないといけないと思っています。亜由美先生のご指導の下、おかげさまでここまで展開してきた施設も数字がきちんと伴っています。
補助金が減ったとか、子どもの数が減ったとか色々と仰る方もいらっしゃいますが、福祉はそこにフォーカスするものではないと思っています。もし補助金が打ち切られてしまったとしても、また新たな補助金を市に働きかけて作れば良いと思うのです。そういうことに関しては率先してやってきたという自負はあります。僕が信念をもってやっていたら、あとから補助金がついてきた、なんてこともありました。補助金というのは、実際に現場で動いている人だからこそ、本当に必要なものなのかどうかがわかると思うんですよね。だからこそ、市に働きかけること、補助金が出る・出ないに関わらず、想い・信念をもってやる、というのが大切なことだと感じています。以前、増美保育園が中心となって市に要望した一つに、「緊急時には、市の要請を待たずに園長の裁量で休園することができる」ということがあります。川越市の民間保育園は川の近くにある園が多いため、安全性を確保するための要望だったのですが、まさに現場の声から挙がった働きかけでした。
そういった行動の中でも、やはり大事なことは、人と人が繋がっていくということです。これが根底にあるからこそ出来ることがまだ沢山あると思っています。 例えば、地域の自治会の会長さんの名前を知っているというのは重要ですね。地域と密接な関係になっていかないと、何かあった時に「あの保育園はいらないよね」となってしまうことだってありうるのです。
林:そうですよね。そうやって地域と繋がっていくこと、人と人との繋がりを強くしていくことの大切さを改めて伺えて、とても素敵な時間でした。ありがとうございました!これからも奥様と共にご夫婦で園を盛り立てていってください!心より応援しています!
鈴木:こちらこそありがとうございました。夫婦共に働くことができ、おかげさまでスタッフにも恵まれています。今日は亜由美先生とお話し出来て本当に良かった。息子さんをお預かりしていた頃に戻ったような気持ちになりました。是非園にもまた遊びに来てくださいね。
林:はい!今度息子と一緒に伺いたいと思います!ありがとうございました!
会社概要
【事業内容】
・認可保育園(増美保育園/増美保育園 川越/増美保育園 田町)
・分園(本川越分園/川越駅前分園)
・地域子育て支援事
【所在地】〒350‐1131 埼玉県川越市岸町3-28-1
(TEl)049-245-2740
【HP】https://www.masumi-h.ed.jp
最近の投稿
- 2026.01.30
- 税務調査で「追徴課税」になったら、いくら、いつまでに納めるのか?
- 2026.01.13
- リーダーシップへの舞台裏Vol.28 ~今を駆ける社長のインタビューシリーズ~
- 2025.12.08
- リーダーシップへの舞台裏Vol.27 ~今を駆ける社長のインタビューシリーズ~
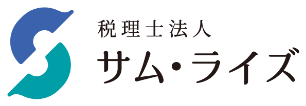
 0800-800-3602
0800-800-3602 お問い合わせ
お問い合わせ アクセス
アクセス