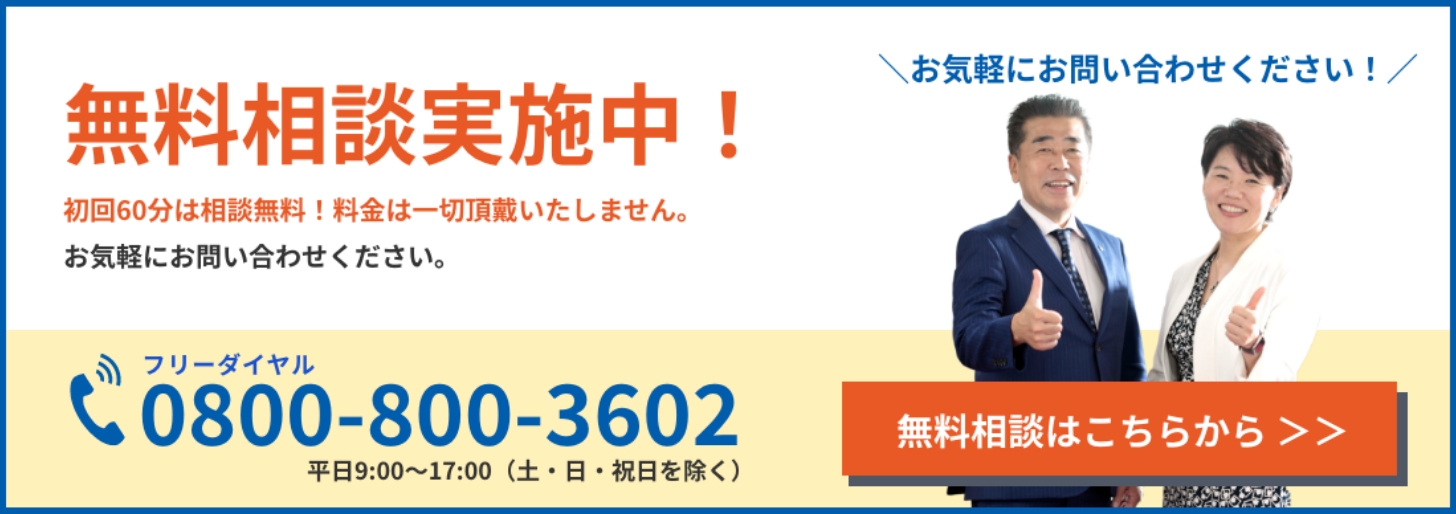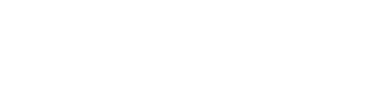リーダーシップへの舞台裏Vol.21 ~今を駆ける社長のインタビューシリーズ~

目次
あわてず急いで正確に!!
現場発の発想力と“鉄の絆”が導く、ものづくりの新章
創業から60余年。地域のインフラを支える鉄工のプロフェッショナルとして、震災も乗り越え、時代の変化に対応しながら歩み続けてきた有限会社渡信鉄工。その根底には、どのような想いがあるのでしょうか。今回は、会長である渡邉基史氏に、製品開発へのこだわりや人材育成、そして世代交代を見据えた今後の展望まで、じっくりと話を伺いました!
【プロフィール】
1962年、仙台市生まれ。高校では天文部に所属し、八戸工業大学土木部に進学後、中退。1983年、父・渡邉信男氏が創業した有限会社渡信鉄工に入社(当時:名取市)。1989年に岩沼市への本社移転を経て、1999年に代表取締役社長に就任。
2002年には第二工場を稼働させ、2011年の東日本大震災では甚大な被害を受けながらも事業を再建。2021年には新たに開削用角覆工板の製作を始め、リース対応を強化。現場から生まれる発想力と対応力を強みに、全国から信頼を集めている。2024年より会長に就任。また、日本クレーン協会東北支部支部長として、各種講習の講師も務める。趣味はトラックでのドライブ、温泉巡り、海釣り、人工衛星探し。「これまで無理をしてきたので、これからはのんびり過ごしたい」と語るが、その背中には、ものづくりと仲間への変わらぬ情熱がにじむ。
現場の声から生まれる、リアルな鉄工ものづくり
倉橋:さて、第21回目となる今回お話を伺うのは、有限会社渡信鉄工(わたしんてっこう)の会長、渡邉基史さんです!渡邉会長、本日はどうぞよろしくお願いいたします。早速ですが、御社の概要や事業内容について、詳しくお聞かせいただけますか?
渡邉:はい、うちは鉄工所なんですが、主に下水道や土木工事に使う鉄製品の製作や修理をしています。住宅などの建築系ではなくて、たとえばショベルカーの“バケット”(土を掘る先端の部分)の修理や、「立坑(たてこう)」と呼ばれる下水道工事用の構造物をつくったりしています。また、「推進工事」で使う下水用のパーツもいろいろ手がけています。最近は新しい取り組みとして、リース用の新製品開発も始めました。たとえば、道路を掘って下水管や水道管などを埋設する際、通常は工事後に埋め戻して元に戻す必要がありますよね。そこで、その手間を減らすための専用の蓋を開発しました。これまでは鉄板を敷くだけでしたが、ズレやすくて危険だという声が多くて。そうした課題を解決するために作ったのが、うちの「開削用角覆工板」です。今までありそうでなかった製品なんですよ。
倉橋:なるほど、鉄工所と聞くと、どこか昔ながらの職人仕事をイメージしがちなんですが、実際には下水道工事や重機の部品修理だけでなく、時代に合わせた製品開発までされているんですね。なかでも「開削用角覆工板」は大ヒットと伺いましたが、事業の大きな転機になったのではないでしょうか?
渡邉:そうですね。最初のきっかけは、ある現場での出来事でした。とても固い地盤に管を埋設し、作業後に蓋をしなければならなかったんですが、使っていた「敷鉄板」がずれてしまい、「これは危ない」ということで、なんと工事が2か月も止まってしまったんです。そのとき「何かいい方法はないか」と相談があって、実際に現場を見に行ったら、「鉄板にずれ止めをつければいい」とひらめいたんです。そこから商品開発がスタートしました。開発は3年前。販売初年度と翌年は、私一人で営業していましたが、宮城県内とその周辺が限界で。せっかくいいものができたのに広がらないのはもったいないと感じていたところ、土留めを扱うリース会社さんに声をかけたら、「ぜひやりましょう」と快く応じてくれて。全国展開している会社だったので、そこから一気に広がりました。今は、ものづくりの仕事自体が減ってきていて、「このままではいけない」と感じています。だからこそ、今はこのリース分野に力を入れて、新たな展開を進めているところです。
倉橋:まさに現場のニーズから生まれた“リアルなものづくり”ですね。しかも、それがしっかり形になって、全国に広がっているというのは、本当に素晴らしいです!
渡邉:ありがとうございます。ただ、この「開削用角覆工板」なんですが、実は特許は取れなかったんですよ。仕組みがあまりにもシンプルすぎて(笑)。でも、その代わりに実用新案は取得しました。やっぱり模倣されないようにという意味でも、「こういうものをうちが作りました」という証明になるかなと思って。ほかにも、現場の声をきっかけに開発した製品がいくつかあって、「開削用角覆工板」も含めて、これまでに特許1件、実用新案は4件取得しています。
倉橋:現場の声をしっかり受け止めて、それを着実に製品化しながら、実用新案を含めて、しっかりと製品を守る手を打たれているんですね。

現場の声から生まれた「開削用角覆工板」。敷鉄板のズレによる事故を防ぐために開発され、工事の安全性と効率を大きく向上させました。
苦境を乗り越えて、次代へ――
震災と世代交代の記録
倉橋:常に現場に寄り添ったものづくりをされてきた渡邉会長ですが、その裏側には、きっと並々ならぬご苦労もあったんじゃないかと想像します。中でも「これはきつかった…」という出来事があれば、ぜひお聞かせいただけますか?
渡邉:やっぱり一番つらかったのは、東日本大震災のときですね。うちの工場は仙台空港のすぐそばにあるんですけど、津波の被害をまともに受けました。津波の高さは、うちのあたりでだいたい1メートル20~30センチくらい。工場の機械はほとんどダメになってしまいました。震災が起きてすぐの頃は、現場はどこも工事が止まり、しばらくは仕事にならなかったですね…。仕事が少しずつ再開できるようになったのは、3か月ほど経ってからです。幸いその頃は資金的にも余裕があったので、中古の機械を買って修理したり、メーカーに修理を依頼したりして、なんとか乗り越えました。ただ、最終的には3億円くらいの損害になっていました。それに建物自体もダメージを受けていたことが後からわかって、6年ほど前に工場を建て替えました。そのときに初めて大きな借金を抱えましたけれど、それ以外はなんとか自力で乗り切ってきたんです。本当に、周囲の方々に助けられましたよ。「車がないなら貸してあげるよ」なんて声をかけてくださるお客様もいて、地域の皆さんには感謝しかありません。
倉橋:そうだったんですね…お話を伺っているだけでも、胸が締めつけられるような状況ですが、そんな極限の中でも機転を利かせて、一歩ずつ復旧に向けて動かれた姿勢に、本当に頭が下がる思いです。地域の方々やお取引先との絆にも支えられながら、そうして乗り越えてこられた道のりが、今の渡信鉄工さんの礎になっているんですね。そして昨年、ついに創業60周年を迎えられたと伺いました。本当におめでとうございます!
渡邉はい、ありがとうございます。私は2代目なんですが、社長に就任したのが36歳の時だったんです。そしてちょうど昨年、会社が60周年を迎えたタイミングで、今の社長であるうちの息子も、たまたま同じ36歳になりましてね。良い節目だと思って「社長をお願いするから」と声をかけたら、「やってみる」と言ってくれて。そんな流れで、私は会長として支える立場に回らせてもらっています。
倉橋:息子さんも同じ年齢でバトンを受け継がれたというのは、まるで運命のようなお話ですね。代替わりというのは会社にとっても大きな節目かと思いますが、実際に世代交代をされて、どのような変化を感じられましたか?
渡邉:今の社長になってからは、事務所まわりの業務がずいぶん効率化されましたね。これまでアナログだった作業に、息子が自作のプログラムを導入してくれて、本当に仕事が楽になりました。ただ、良いことばかりというわけでもなくて、新しい課題も出てきています。うちはこれまで主に下水道関連の仕事をやってきましたが、インフラ整備っていうのは、ある程度まで進むと、仕事が自然と減ってくるんですよ。最近では、下水道工事の案件もだいぶ少なくなってきていて。もちろん、まったく無くなったわけではないですけど、仕事量としてはかなり減っているのが実情です。それもあって、今の社長は新しい方向を模索しているみたいです。私もいろいろと相談には乗っていますが、やはり大きな設備投資となると、簡単に決断できるものではないですからね。私がまだ現役で会社に関わっていることもあって、なかなか息子ひとりで最終判断を下すのは難しいところもあるようです。時代の流れもありますし、今の社長が一番大変なのかもしれません。だからこそ、私はもう少しだけ頑張って、彼に何か次の“柱”になるようなことを残してやりたいと思ってるんです。リース用の製品も、これまでにいくつか世に出してきましたけど、まだまだ世の中に必要とされるものがあるんじゃないかと思って。そんな思いで、もうひと踏ん張りしているところです。
倉橋:世代が変わり、時代が変わっても、変わらないのは“会社を良くしたい”という想いですね。親子でバトンをつなぎながら、会社の未来を見つめている姿がとても印象的です!

信頼と共に!チームで挑む
これからのものづくり
倉橋:それにしても、時代の流れに合わせて新しい一歩を踏み出すには、会長や社長だけでなく、会社全体が一丸となることが欠かせませんよね。社員の皆さんとは、どんな思いで向き合い、どのような関係を築いてこられたのでしょうか?
渡邉:うちでは、ものづくりの現場でも「みんなで考える」ということを大事にしてきました。例えば、何か新しいものを作ろうと思ったとき、普通だったら上から「これをやって」と指示が出て、担当者がひとりで考えるケースが多いと思うんですが、うちは違うんです。私が「こういうのを作れないかな」と思ったら、まず現場のリーダーに相談します。するとリーダーがメンバーを集めてアイデアを出し合い、全員参加で商品開発に取り組んでくれる。そうして生まれた製品も、リース品から販売用のものまでいくつかありますが、どれも社員みんなの知恵と努力の結晶だと思っています。他にも、工場のレイアウトを工夫して残業を減らすなど、現場の改善もみんなで話し合いながら進めてきました。一人で考えても限界がありますから、やっぱり現場の声って大事ですよね。だからこそ、日頃からの人間関係づくりも意識していて、社員旅行や懇親会などでコミュニケーションを深めるようにしています。今年の3月にも、急きょ思い立って、社員を連れて京都と愛知に旅行へ行きましたね。愛知県では、うちと同じような仕事をしている長年の付き合いのある会社さんにお邪魔して、工場を見学させてもらったんです。もう20年以上のお付き合いになるかな。社員を連れて行くのは初めてでしたが、みんな本当に喜んでくれて。「同じようなことやってるけど、こういうやり方もあるんだ」って刺激を受けたみたいです。こうした交流からも、また新しいアイデアや改善点が生まれてくるんですよ。
倉橋:社員一人ひとりの知恵を活かす“全員参加”のものづくり、まさに理想的なチームの姿ですね。そうした現場の声を取り入れる柔軟な姿勢が、これからの変化の時代にはより一層大切になってくるように感じます。では改めて、これからの渡信鉄工として、どんな未来を描いていらっしゃいますか?
渡邉:そうですね…私がこれからやりたいことは、社員たちにもっと“楽をさせてあげたい”ということなんです。ここで言う「楽」というのは、決して怠けるという意味ではなくて、段取りが良く、効率的に、そしてスムーズに仕事ができるということ。そういう働き方ができれば、自然と気持ちにも余裕が生まれる。だからこそ、私一人の考えではなく、みんなでアイデアを出し合いながら、どうすればもっと楽に、そして楽しく働けるかを考えていきたいと思っています。それが私の夢です。それからもうひとつの目標として、今は売上全体の1割から1.5割程度を占めるリース事業を、さらに伸ばしていきたいと考えています。リースというのは、全国各地に製品が出ていけば、それだけで収益につながる仕組みです。物を作るだけでなく、そうした継続的な収入の柱が育てば、会社としてもより安定しますし、社員の働き方にも良い影響が出ると思っています。
倉橋:本当に、社員の皆さんの働きやすさを第一に考えておられるのが伝わってきます。「楽をする」ことが、ただの効率化ではなく、現場の工夫やチームの知恵を引き出すという視点に繋がっているのが、渡信鉄工さんらしいですね。本日は貴重なお話をありがとうございました!地域に根ざしながらも、常に時代の先を見据える姿勢に、多くを学ばせていただきました。今後のさらなるご発展を心よりお祈り申し上げます。


2025年春、社員旅行で訪れた京都・名古屋。現場を離れて交流を深める貴重なひとときとなり、「また明日から頑張ろう」と自然に笑顔がこぼれる時間でした。
会社概要
【事業内容】
●金属製品製造業(製造・修繕・加工)
●土木・下水工事用リース商品開発・製造
●現場作業
【所在地】
〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字新南長沼30-6
(TEL)0223-22-3543
(FAX)0223-23-3446
最近の投稿
- 2026.01.30
- 税務調査で「追徴課税」になったら、いくら、いつまでに納めるのか?
- 2026.01.13
- リーダーシップへの舞台裏Vol.28 ~今を駆ける社長のインタビューシリーズ~
- 2025.12.08
- リーダーシップへの舞台裏Vol.27 ~今を駆ける社長のインタビューシリーズ~
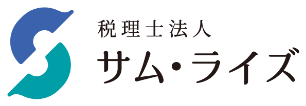
 0800-800-3602
0800-800-3602 お問い合わせ
お問い合わせ アクセス
アクセス