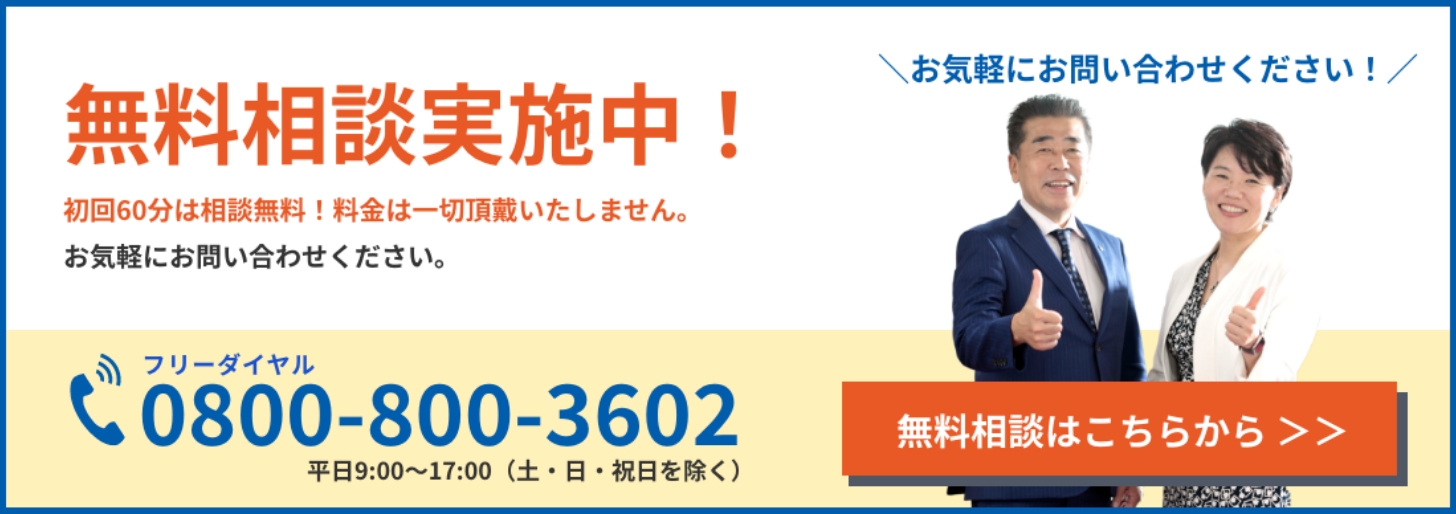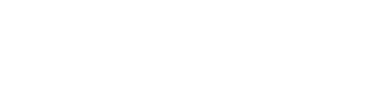リーダーシップへの舞台裏Vol.20 ~今を駆ける社長のインタビューシリーズ~
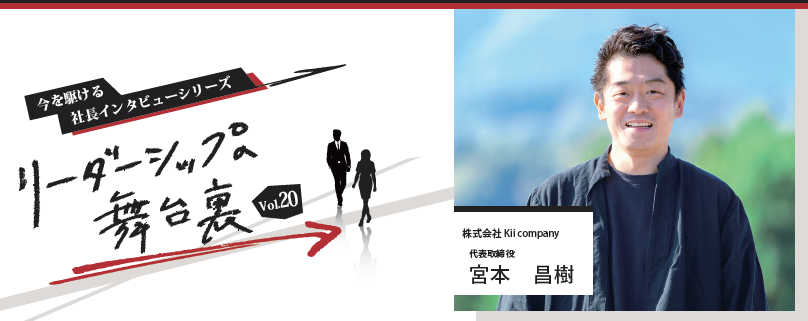
目次
ただの再建じゃない、人と地域をつなぐ
“風呂屋ビジネス”の最前線
~地域にもう一度“湯けむり”を~
「リピート率が命」と言われる温浴施設で、どうすれば “また 来たくなる空間”をつくれるのか―。宮本社長の丁寧なリサーチ、明確なビジョン、そして“風呂屋を人生ごと背負う”という熱い覚悟に迫りました!
【プロフィール】
1986年、和歌山県生まれ。
立命館大学文学部在学中、学園祭の企画運営やボランティア活動に携わる中で、社会課題をビジネスで解決する「社会起業家」を志すようになる。
大学卒業後は東京都内のベンチャー企業に入社し、営業職として3年間勤務。 27歳で地域活性化を目指し、埼玉県の株式会社温泉道場へ転職。以降11年 間にわたり、温浴施設の現場運営や業績改善を担いながら、経営全般を学ぶ。 2020年には、三重県の子会社・株式会社旅する温泉道場(2016年設立)の代表取締役に就任。同年、新型コロナウイルス対応のため、三重県へ移住。 2025年1月、社名を「株式会社Kii company」へ変更。現在は、埼玉県や愛媛県の企業役員も兼任しながら、全国各地での地方創生や温泉施設の再生支援にも積極的に取り組んでいる。
プライベートでも温泉巡りを楽しむほか、料理や日本酒にも親しむ。
温泉愛から始まったビジネス革命―
“正解のない業界”で勝負する理由
倉橋:さて、第20回目となる今回お話を伺うのは、株式会社Kii company(キイカンパニー)代表取締役社長の宮本昌樹さんです!
宮本社長、本日はどうぞよろしくお願いいたします。早速ですが、御社の概要や事業内容について 、詳しくお聞かせ いただけますか?
宮本:はい、よろしくお願いいたします。私たち株式会社Kii companyは、紀伊半島を中心に、民間や行政が抱える不採算温浴施設の経営を引き継ぎ、リノベーションなどを通じて再生に取り組んでいる会社です。もともとは2016年12月に「株式会社旅する温泉道場」として設立し、 2025年1月に「株式会社Kii company」へと社名を変更しました。現在は三重県で2店舗を運営しています 。1つ目は四日市市の「おふろcafé湯守座」、2つ目はいなべ市の「いなべ阿下喜ベースおふろcaféあげき温泉」です。
倉橋:不採算の施設を引き継いで、さらに再生していくって、かなり大変な取り組みですよね。あえてそういう難しい分野に特化して、事業として展開しようと思ったのはどうしてなんでしょうか?
宮本:そうですね、そもそも僕自身が温泉好きっていうのが大前提にあって(笑)。でも、それだけじゃなくて、温泉ってビジネスとして見たときに、すごく大きな可能性があると思ってるんです。世界的に見ても、温泉をちゃんとビジネスとして成立させている国って、実はそんなに多くないんですよ。そういう中で、日本は温泉資源がとても豊富で、観光産業としてはかなり優位なポジションにあるはずなんです。でも実際の温泉業界って、経営という面ではまだまだ発展途上というか 、古くからの家 業スタイルで続いているところがほとんどで、ビジネスとして体系化されていない部分が多いんですよね。だからこそ、ちゃんとビジネスとして組み立てていけば、再生のチャンスはまだまだあるんじゃないかと。今のところ、業界全体として「これが正解」というモデルが確立されていないので、誰もが手を出しにくい状況ではあるんですけど、逆に言えば、だからこそ挑戦する意味があると思っています。
倉橋:「温泉業界にまだ正解がないからこそ、そこに挑む面白さがある」という発想や視点って、やっぱり宮本 社長ご自身のこれまでのご経験がベースになっているんだろうなと感じます。ぜひここで、これまでのキャリアについても教えていただけますか?
宮本:はい。最初は東京・五反田にあるベンチャー企業で、3年間ほど働いていました。そこでは、高齢者施設に美容師さんを派遣したり、施設内で洋服の販売会を開いたりといった、「民間サービスを福祉の現場に届ける」ような事業をやっていました。その後、埼玉にある「株式会社温泉道場」に転職して、そこで約11年勤めました。途中からは、三重県にある子会社の社長を任されることになって、最終的にはそこからスピンアウトして、独立したという流れです。
倉橋:なるほど。介護や福祉、そして温浴と、一見ジャンルは違って見えますが、どちらも「人の暮らし」に深く関わる領域なんですね。そうした現場でのご経験が、今の宮本社長の事業スタイルにしっかり活きているのが伝わってきます。
【リニューアルオープン後】

コロナ禍で経営に困っていた行政所有の温泉施設「阿下喜温泉あじさいの里(三重県いなべ市)」を2024年にリノベーションし、「いなべ 阿下喜 ベース」としてリニューアルオープンした再生事例。現代のライフスタイルに寄り添ったデザインと居心地の良さが話題を呼び、たくさんの人に「落ち着きと癒し」を届ける場所へと生まれ変わりました。経営も順調に進んでいます。
“通いたくなる風呂屋”のつくり方
倉橋:実際にホームページなどを拝見して感じたんですが、お店のデザインがとても洗練されていて、若い世代にもウケそうな雰囲気ですよね。従来の温泉施設とはかなり印象が違うなと。そういったところも、やはり戦略的に意識されているんでしょうか?
宮本:そうですね。もちろんデザインは意識してつくってはいるんですが、最初から「若者向けを狙おう」と思っていたわけではないんです。どちらかというと、自分たちが「こんな風呂屋があったら通いたいよね」と思える場所をつくろう、っていう感覚が出発点でした。でも、ビジネスとしての視点で言うと、温浴施設って常にお湯を沸かし続けてるので、エネルギーコストがとにかくかかるんですよ。だから、お客さんに来てもらえないと、もうシンプルにお店として成立しない。今の時代って、「ただお風呂に入るだけ」じゃなかなか選ばれにくいと思っていて。だからこそ、私たちは“お風呂以外の楽しみ方”をいくつも仕込んでるんです。たとえば、カフェでゆっくりしたり、読書ができたり、ちょっとしたイベントがあったり。そうやって「お風呂+α」の体験を提供することで、いろんな目的を持った人が来やすくなるし、より多くの方に足を運んでもらえる場になっていくと思っています。
倉橋:へぇ~そうなんですね!となると、出店前のリサーチとか、かなり丁寧にやる必要がありそうですね。お店の方向性を決めるには、スタッフさんのスキルや感覚もかなり大事になってきそうです。
宮本:そうですね、お店を出すっていうのは 、僕にとってはすごく長 期的な プロジェクトなんです。ざっくり言えば、1店舗オープンするのに、構想から実現まで3年~5年くらいかけるイメージですね。そのリサーチも含めて、基本的には全部自分でやっています。誰かに任せるというより、完全に自己責任で取り組んでいる感じです。というのも、温浴施設って一度始めたら簡単にやめられないんです。飲食店みたいに「ちょっとやってみて、合わなかったら閉める」っていうスタイルではない。やるからには最低でも10年、できれば20年は続ける前提で計画を立てなきゃいけません。だから、初期投資の設計から契約の内容、数年後の追加投資や発展の見通しまで、とにかく先のことまでしっかり考える必要があります。実際に10年後の姿がリアルに思い描けるかどうか、それがひとつの大きな判断基準になっています。とはいえ、僕にとってはそれが“普通”なんですよね。たまに驚かれますけど、自分の中では自然な感覚というか。例えるなら、家を買うのに近いかもしれません。家を買うときって、自分のライフスタイルとか、将来どこに住みたいか、家族関係とか、いろんなことを考えて決めますよね。僕にとってお店をつくるって、その感覚とすごく似ていて、「この場所で10年、20年やっていけるかどうか」をじっくり見極めながら、1店舗ずつ決めています。
倉橋:そういったマーケティングって、具体的にはどうやって管理されてるんでしょうか?数字の分析だけじゃなくて、利用者の“生の声”みたいなものを、いつ、どんなふうにキャッチしてるのかがすごく気になります!
宮本:そうですね、やっぱり一番は、地元の人と直接話すことですね。飲みに行ったり、実際にその地域に泊まってみたり。とにかく、その街が持っているポテンシャルを、自分の目でしっかり見て感じるようにしています。それはオープン前もそうですし、オープンしてからもずっと続けています。例えば今日も僕、お店に出てるんですが、普通にお客様のゾーンでデスクワークしていれば会話が自然と耳に入ってきますし、何人組で来てるのかとかも見えてくるんですよ。たとえば、常連さんが「こないだ◯◯の風呂屋行ったけど、あそこのサウナ良かったよ」なんて話していたり。そういう会話を、意識して聞いてますね。スケジュール的には、週に1日だけ埼玉の本社のオンラインミーティングがあって、その日は在宅。あとは本社っていう拠点も特にないので、基本どちらかの店舗に出勤して、バックオフィスにいたり、お客さまのいるスペースに顔を出したりしています。たぶん、世の中のいわゆる“経営者”とはちょっと違うタイプかもしれないです。もともと支配人をやってたので、その延長で「自分がつくりたい世界観のお店を、コツコツ形にしていってるだけ」という感覚なんですよね。だから、よくある「お客様アンケート」とかって、僕はあんまりやらないです。製造業とかだとニーズを拾って分析して…っていうのが大事だったりすると思うんですけど、僕はもう、現場に出て自分で感じ取ったほうが早いって思ってます。それに、僕らが手がけているのは“赤字の施設を再生する”という、なかなかハードなスタート地点なんですよ。つまり、「お客さんの声を丁寧に拾って、それに応えていけば黒字になる」のであれば、前の経営者がとっくに成功してたはずなんです。だからこそ、お客さんの“期待通り”じゃなくて、“期待をちょっと超えるような提案”をしないと意味がないんですよね。そこを目指さないと、再生なんてできないと思っています。
倉橋:なるほど…“数字より現場”っていうスタンス、すごく説得力があります!!

小さな風呂屋から広がる、
大きな可能性
倉橋:では、そんな“現場主義”を大切にされている宮本社長が、人材採用についてどんな視点をお持ちなのかも、ぜひ伺ってみたいです!
宮本:そうですね、おかげさまで、最近は “地方創生”とか“地域活性”に関心のある学生さんとか、あとはサウナやお風呂が好きっていう子たちが、全国から興味を持ってくれるようになってきました。実際、そういった学生の採用は積極的に行ってます。それと最近特に増えてるのが、地元の高校生からの問い合わせですね。アルバイト希望だったり、就職についてだったり。なので、来期からは本格的に高卒採用も始めようと思っていて、今その準備を進めているところです。やっぱり、ローカルで事業をやっている以上、「人手不足」っていうのは今後ますます大きな課題になると思っているので。だからこそ、「学生たちに選んでもらえる会社」にしていく必要があるなと感じています。そのために、ちょっとユニークな福利厚生を考えてみたり、僕自身がYouTubeに力を入れて発信したりもしてるんですよ。今やってるチャンネルは、僕個人で温泉経営のノウハウやリアルな話を届けるっていうコンセプトでやっていて、採用にもつながるといいなと思って続けています。
倉橋:福利厚生を工夫したり、YouTubeでの発信に力を入れたりと、採用にもいろんなアイデアが詰まっていて、聞いていてとてもワクワクしました。まさに “働いてみたくなる会社”ですね!では最後に、今後の展望についてもお聞かせいただけますか?
宮本:ありがとうございます。そうですね…大きなところで言うと、やっぱり「閉店する温泉施設を減らしたい」というのが、自分の中での根本的な想いとしてずっとあります。だから、今後も店舗数は増やしていかないといけないなと思っています。実際に今、来年度に和歌山で新しい店舗をオープンできるかもしれないという話が進んでいて、その後の展開も含めていろいろと構想を練っているところです。次にやってみたいなと思っているのは、地域の高齢 者の方たちがボランティア的な形で関わってくれるような、小さな銭湯のような施設ですね。
「地域でいちばん小さな風呂屋って、どんな形なんだろう?」っていうところをテーマに、サイズ感も含めて、新しい形の店づくりにチャレンジしたいと思っています。それと、以前からYouTubeでも発信しているんですが、温泉業界って、他の業種と違って学べる本も少ないし、雑誌やネットにも情報があまり出ていないんですよ。僕自身も始めたばかりの頃は、何から学べばいいのか全然わからなくて苦労したんです。だからこそ、これからはもっと温泉経営のノウハウやセオリーをオープンにしていきたいと思っていて、 YouTubeでもそれをどんどん発信しています。5年くらいかけてそうした情報を積み重ねていく中で、「自分たちにも風呂屋、できるかも!」って思える若い人が増えてくれたら嬉しいですね。
倉橋:「地域でいちばん小さな風呂屋」という発想がとても新鮮で、どんな場所になるのか、今から楽しみです!
本日は、温浴業界への熱い想いや現場に根ざした経営のリアル、そしてこれからの展望まで、たっぷりとお話を聞かせていただき、ありがとうございました。宮本社長の挑戦が、地域に、そしてこれからの世代に、温かく広がっていくことを楽しみにしています!


宮本社長のお話で印象的だったのは、「若手のアイデアこそが、これからの会社の原動力になる」という言葉。社長自らも足を使ってリサーチを重ね、社員同士も意見を出し合いながら、アイデアを「まずはやってみる」という企業文化がしっかりと根付いているのを感じました。今ある事業を守るだけでなく、進化させていこうとするその姿勢に、今後の展開がますます楽しみになりました。
会社概要
【事業内容】
・温浴・宿泊・飲食施設の運営
・温浴施設再生支援
・地方創生事業全般など
【所在地】
〒512-0911 三重県四日市市生桑町311
(TEL)090-7281-5853
最近の投稿
- 2025.12.08
- リーダーシップへの舞台裏Vol.27 ~今を駆ける社長のインタビューシリーズ~
- 2025.11.13
- リーダーシップへの舞台裏Vol.26 ~今を駆ける社長のインタビューシリーズ~
- 2025.10.31
- 税務調査の事例 「税理士の介入により、追徴課税を減額できた」編
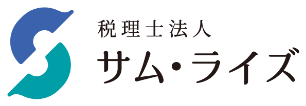
 0800-800-3602
0800-800-3602 お問い合わせ
お問い合わせ アクセス
アクセス